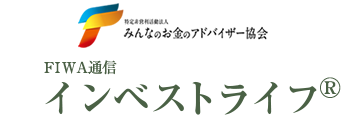【Vol.269】寄稿 インディ君活用法
連載:FIWAインディくん活用法
龍谷大学経済学部教授
竹中 正治氏
投資シミュレーションソフト「FIWA®インディくん」の活用法
その4 各種インデックス間のリスク分散効果(応用編)
プロトタイプ版(無償)、本格版(年間利用料11,000円(税込))
https://fiwa.or.jp/simulation/(←インディくんのサイト)
FIWA®インディくんの活用法4回目の解説です。前回は「2.複数の株価指数の過去データに基づく定額積立投資のケース」の機能を使って、日本と米国の株価指数の間には、ある程度のリスク分散効果があることをインディくんで確認しました。
具体的には日米の株価指数ファンド双方を対象に、比率を10%ずつ変えた合成ポートフォリオのリスク・リターン分布を描くと、図上には(リスクを横軸、リターンを縦軸)左に凸の有効フロンティアが生じました。つまり日米双方のファンドを合成して保有することで相対的にリスクを下げることができるわけです。ただしそのリスク低減効果は、それほど強いものではありませんでした。
今回は同様のシミュレーションを他の株価指数にも広げてみましょう。例えばNISAの積立投資枠で人気の世界株価指数(MSCI AC、オルカン)は、世界中の主要国株式を対象にしているという点で既存の株価指数の中では最もリスク分散が高いと言えます。したがって理論的には、リスク対比のリターンも高い(リスク・リターン図上の左上に位置する)指数であることが期待されます。実際にそうなるでしょうか?その点にも注目してみましょう。
使用する機能は前回同様「2.複数の株価指数の過去データに基づく定額積立投資のケース」「最適ポートフォリオ」です。シミュレーションの前提としては過去20年間、配当再投資ベースでやります。またインディくんのシミュレーションは全て円換算ベースであることを念頭においてください。
まず米国株価指数(画面上の記号:a1)と日本株価指数(同a2)を選んで「最適ポートフォリオ」を押すとグラフと一緒に以下の表が得られます。
PCのスクリーンに表示された上の表をコピー&ペーストでエクセルにそのまま張り付けてください。画面からコピペする際にはまずカーソルを表の一番左上に落として、マウスの左ボタンを押したまま、右下の端までドラッグして範囲指定します。次に右クリックで「コピー」を選んでエクセルに張ると、数字データをエクセル上でそのまま使えます。画像コピーでは数字情報が使えません。
こうしたエクセルの操作は、エクセルの利用に慣れていない方には、よくわからないかもしれません。そういう方は、今年6月20日、7月18日に開催する「FIWA®インディくん活用講座」(←講座参加登録のサイト)にご参加いただけると、エクセルの使い方まで含めてご指導いたします。
次に日本株価指数(a2)と欧州株価指数(b3)を選んで同様の操作をすると次の表が得られますので、同様にエクセルに貼り付けてください。
次は中国株価指数(b5)、インド株価指数(b6)で同様の操作をすると、以下の表を得ます。同様にエクセルに貼り付けてください。
最後は世界株価指数(a4)ですが、これは世界の株式市場を対象にしているので、これ単体100%にして「計算する」を押すとリスク18.3%、リターン12.4%を得ます。これもエクセル上に記載しておきます。
以上で準備ができました。最後にエクセルで作図をします。「リスク量」をX軸、「年率利回り(リターン)」をY軸にしたひとつの散布図上に以上のデータを表出し、整えたものが次の図です。こうした散布図の作成もエクセルに不慣れな方は、どうすればよいか分からないと思いますが、それほど難しくはありません。
ただし操作の手順を全部文章で説明すると長くなるばかりで、かえってわかり難いものになります。上記に記載しました通り「FIWA®インディくん活用講座」にご参加いただけると、エクセルの操作を含めて手ほどきいたします。
必ずしもベストではない世界株価指数
さて、出来上がった図を見て何がわかりますか?前回見た通り、青点で示した日本と米国株価指数の間には弱いリスク分散効果があり緩やかに左に凸の形状で、かつ図上で最も左上、つまりリスク対比で高いリターンの位置に分布していることがわかります。
一方、オレンジ点で示した日本と欧州株価指数の間にはほとんどリスク分散効果がなく、オレンジ点の分布は直線に近いです。しかも欧州100%のポートフォリオは米国株価指数よりリスクが高くリターンが低い位置にあります。
また、赤点で示した世界株価指数の位置は、日米株価指数の描く有効フロンティアの右側に位置しています。これは世界株価指数の中で欧州株価指数は比較的高い比重を占めているのですが、そのリスク・リターンが悪い(高リスク・低リターン)ために、それを含む世界株価指数が右下に引っ張られているのです。中国を含む途上国株価指数についても欧州株価指数と同様のことが言えます。
1990年代以前は、各国の株式指数が別々に変動する傾向が強かったため、株式の国際分散投資は対象国・地域を広げるほどリスク低減効果があったといわれています。ところが、金融・投資のグローバル化が進んだ90年代以降は、各国の株価変動の同調性が高まり、その結果、国際分散投資のリスク低減効果が薄れたのです。そうした事情が世界株価指数のリスク低減の度合いを押し下げていると考えられます。
最後に、緑点で描いたインド株価指数と中国株価指数の間にはリスク分散効果があり、双方の比率を変えることで左に凸の有効フロンティアが現れています。ただし図上のかなり右端に位置しており、やはりリスク対比のリターンは良くありません。
筆者の株式ポートフォリオは、2006年以降これまで、日本株と米国株を中心に構成してきました(インデックスと個別銘柄)。筆者自身、インディくんを使った過去データの検証で、その判断が正しかったことを確認することができました。
もちろん、以上のシミュレーションはあくまでも過去の結果であり、将来も同じであることを保証しません。今後欧州やインド、中国の株価指数のリスク対比のリターンが大きく改善すると予想する方は、そうした国の比率を上げるのがよいでしょう。
最後に課題です。上記は過去20年間のシミュレーションですが、過去10年ではどうなるでしょうか?できる方はやってみてください。結果は次回お見せいたします。
(次号に続く)