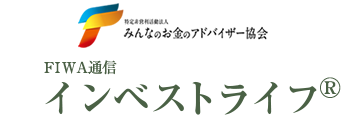【Vol.269】FIWAサロイン塾講演より(講演)
株式、債券とインフレの関係
特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会 代表理事 会長
ファイナンシャル・ヒーラー 兼 投資教育家
岡本 和久CFA
レポーター:赤堀 薫里
(この原稿は3月16日に開催されたFIWA®サロイン塾における岡本の講演を一部ご紹介するものです)
株式と債券を比較してお話します。投資対象として株式と債券の強みと弱点。株式の強みというのはまず増「価」証券であること。価値が増加していく有価証券。これは特徴です。株式の2番目の特徴は、企業が保有している資産は企業全体が持っている資産から借金を全部返済した残りの部分です。それは製造業の工場であったり、オフィスビルだったり、さまざまな形の資産になります。つまり株式は、借金を全部払った後、資産の裏付けがあります。
債券は通常、返済される元本や金利が最初に決まっているので、物価が上昇すればその債券の価格は下落する。例えばこんな極端な例です。ある人が5,000万円のマンションを全額ローンで買ったとしましょう。買った途端にインフレが起こり、あっという間にマンションの値段が7,000万円になりました。その人は大喜びです。なぜなら、買った物件は大幅値上がりしているのにローンの残高は同じだからです。いくらマンション価格が上がっても借入金の元本は増えない。逆に、お金を貸した側はがっかりする。それが分かっていれば、お金なんか貸さないで、自分でマンションを買っておけばよかった。実物資産を買っておけばよかったと思うわけです。
反対に、突如としてデフレが起こった。5,000万円のマンションが3,000万円になってしまった。今度はマンションを買った人はがっかりするでしょうね。物件の価格は下がった。でもローンの残高は減らない。お金を貸した人は喜んでいます。こういうことから、インフレのときは物を持つのが得で、お金を貸すのは損。デフレのときは物を持つのが損で、お金を貸すのは得という関係にあることがわかります。
株式を持つということはその発行企業のオーナーになることです。株主になれば、その企業の物的資産を保有していることになる。一方、債券を持つということは、その企業にお金を貸し付けていることになる。だから、インフレのときには物的資産の裏付けのある株式が相対的に良くて、債券の魅力は劣る。
デフレのときは、債券を保有している人に相対的な妙味があって、株式は苦しいということになるわけです。株式の価値は、収益が固定されている債券と比べて、実物資産の価値に基づく部分が多いということです。債券は発行者の信用が裏付けになっています。しかし、株式には物的資産の裏付けがあるわけです。つまり、物価上昇にも比較的強い、残り物には福がある、というのが株式ということです。要するに、株主が保有している資産は、資産全体から借金を全部返した残り物であるということです。
それでは株式の弱点は何でしょう。これは倒産の場合のリスクがあるということです。債券の場合は、絶対に安全とは言えませんが企業が万一倒産をしても、株主よりも先に会社の資産により返済を得ることができる。一方、株式は、会社の資産を全て債務者に対する借金を返済した残りしか残ってない。場合によっては全く何も残っていない。完全にパーとなるということもあり得るわけです。
もう一つの弱み、これは株式市場での株価の変動です。価格というのはまるで企業価値の影みたいなものです。欲望の側からその実体価値に光を与えると、影はすごく大きく見えるので強気になる。弱気の側から光を当てると、影は小さくなってみんなが弱気になる。
歴史的にはハイパーインフレや長期的な大不況が起こることもあります。その場合にもよりますが、こういう異常事態の場合は経済そのものが混乱するので、株であれ、債券であれ、投資環境は非常に悪いか、極めて投機的になってしまう。極端に悪い状態がずっと続いていき、ついに人類が滅亡するというようなことは取り合えず、ないわけですから、そういう意味ではどんな時にも積み立てを続けていくということが、実は非常に効果があります。
重要なことは、株でも債券でもその弱みと強みを理解するということだと思います。株式については増「価」証券、比較的インフレに強い。長期にわたって分散投資することが比較的しやすい長期的な資産形成に向いている。債券は金利が事前に定められた通り支払われる。満期がくれば元本が払われる。そのような特性を十分に理解しながらサテライトの素材として債券を使うのもいいかなと思います。
株は危ない。債券は安心。というのは一般論としては正しいですけれども、平均的な収益率は確かに株式に比べれば債券は低いので、その代わり分リスクは低いと言えます。名目的な元本は保全されても購買力という点で債券のリスクは大きい。要するに、どちらがいいかということではなくて、投資目的に合わせて考えればいいんだということです。
また、最近、デリバティブと呼ばれる派生証券を利用して高い利回りを得るように見せかけられた商品も出回っています。これらは私にとってもどうなっているのかよく分からないような、理解できない仕組みです。一定のシナリオが実現すれば高利回りになる。でも多分実現しないみたいなそういうものです。逆に言えば、異常に高い債券は何かあるなと考えた方が絶対いいと思います。株でも債券でも、異常に高いものは、「甘い蜜には毒がある」のが普通です。大切なことは投資によって自分が何を実現しようとしているのかをはっきり理解して、それにあった運用方針を続けることです。
講演当日の動画は以下のサイトからごらんいただけます。
https://youtu.be/8tXVVVbzmaw
(文責FIWA®)