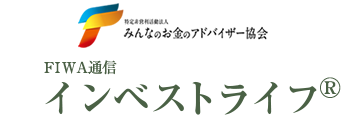【Vol.264】FIWAマンスリー・セミナ講演より(講演2)
私の投資教育20年の変遷
特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会 代表理事 会長
ファイナンシャル・ヒーラー 兼 投資教育家
岡本 和久CFA
レポーター:赤堀 薫里
アドバイザーという仕事がどういう位置づけにあるのかを、私は長期的な視点から話をしたいと思います。
人生を通じての資産運用は決して難しいものではない。ただ一方で非常に激しく変動する相場があります。そのために時として横道にそれてしまう可能性がある。そこで必要なのが伴走者であり、かつ羅針盤でもあるアドバイザーだと思います。専業アドバイザーが必要な時代が来ていると思います。人生を通じての資産の管理は本当に大きな課題になってきている。国や企業に頼るのではなくて、将来の自分は今の自分が支えるという意識は必要になってきています。最も危険な言葉は「なんとかなる」これは現実から逃避しているだけで、人任せにすぎない。世界の金融業界が実体経済と比べて非常に巨大化して複雑化し、しかも市場のボラティリティーが高くなっている。さらに資産運用そのものが、一人一人の人間にとってカスタムメイドのものになってきている。価値観がみんな違ってきている。ニーズが非常に多様化してそれぞれの生活スタイルにあったものになってきている。カスタムメイドしていくというところにアドバイザーの必然性があるわけです。
よく長期・分散・積立の3つをいいますが、私はそこに継続と流出防止のこの二つもいれたい。流出防止はただ単にコストの問題だけではなくて、もっともっと幅広い流出を防止。そういうことを個人が、自分だけでやるには非常にチャレンジングなものです。やはり効率的、かつ無駄のない人生設計にはこれまでほとんど存在しなかった、専業のアドバイザーが不可欠になってきています。
インベストメントチェーンということが語られるようになっています。投信を買います。販売会社に販売手数料を払う。そうすると、アセットオーナー、これは年金、あるいは投資信託だったりしますが、資産の運用会社にお金がいき、そこで資産の運用会社がどのような投資をしようかということを決めて売買を執行する。そのお金が投資先企業の株式なり債券なりに移る。投資先企業はそのお金を使ってお客様のために良いことをして収益を上げ、その収益が消費者、生活者のもとに投資リターンとして戻ってくるという美しい姿です。問題は、大きな販売会社と、消費者の間にものすごい大きな情報格差、あるいは力の格差があるということ。資金力の違いもあります。要するに結局販売会社の言う通りになってしまう。だから大事なのがアドバイザーなのです。ここにアドバイザーが入って中立の立場でこの販売会社、あるいは消費者との間の仲介をしてあげる。そしてアドバイス料をもらう。
忘れてはいけないことは、投信とは人生の中で最も大きな買い物の一つです。運用報酬を犠牲にして資産の増加を図るのは非常に危険です。資産の運用ブームが冷え込んでいるときにも生き延びることができるかどうか。親会社の業績が急激に悪化した時のリスク。親会社にとってどれくらいコミットメントのあるビジネスか。為替ヘッジは原則しないこと。為替だってどうなるのかわからないのでそれぞれの企業の通貨を全部合わせて持っておけばいい。
アドバイザーが相談者と一緒に投資信託説明書を読む。これはすごく重要です。交付目論見書や運用報告書を一緒に読む。質問に答えてあげる。逆にいうとアドバイザーは質問に答えてあげられるだけの知識と経験がないといけない。相談者と一緒に投資方針書をカスタムメイドで作ってあげるということがすごく重要だと思います。
バンガードという投信会社がアドバイザーアルファということを言っています。アドバイザーが適切なアドバイスをすることによって約3%無駄な経費を削減できるということです。年3%です。ものすごく大きい。不適切なアドバイスは長期的な損失を生む。それはライフプランと整合性のないアセットアロケーション。無駄の多いアセットロケーション。リスク許容度を超えた投資対象の選択。長期投資に不適当な銘柄を選択する。リターンに報われないリスクを大幅にとる。コストの高い投資対象を選択する。不必要な回転売買と銘柄の入れ替え。相場の乱高下に心が乱され投資家が投資方針と異なる行動をとってしまう。このようなことを全部あわせていくと、3%くらいのコストになるとバンガードは指摘しています。
それとは別にα(アルファ)、β(ベータ)&γ(ガンマ)という最近の調査結果というか書籍がでています。長期リターン。長期的な市場全体ではゼロサムですが、市場全体の価値が増加していく超過リターンをαといいます。それが市場リターンのβに対して、その市場リターンを上回る超過リターンαをここで獲得する。これが従来のアドバイザーの役割だと思われていた。でも最近はそうではなくてここにγというファクターが入ってきました。これは資産配分と引き出しの順位。全資産での資産の配分。終身年金の活用。動的引き出し戦略。負債を考慮した最適化。こういうことがトータルでみると、γの効果というのは年率で1.59%ぐらいのリターンに相当するといっています。市場のリターンの何%を上回るかということだけではなくて、もっと他のお客様、相談者の収益を上げるためにいろいろなことが実はあるんだということですね。配当金を使ってしまうお客様に対して、こんなに大きな違いがあるんですよということをきちんと指摘をしてあげることが非常に重要だと思います。
講演では、ライフプランを持ったうえで全体像と齟齬のないマネープランを考え、その中で資産運用プランを考えることの重要性と、その手助けをするアドバイザーの存在意義について解説。最後に『人生全体に視点を置いた、その人に最も適したお金との取り組み方、付き合い方を一緒に考える。戦友としてそれを作り出していく。それがアドバイザーというものの本当の役割ではないかと思います』と結ばれました。
(文責FIWA®)