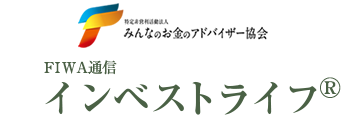【Vol.268】FIWAサロイン塾講演より(講演)
なぜ資産運用が必要か 時間を味方につけるとは
特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会 代表理事 会長
ファイナンシャル・ヒーラー 兼 投資教育家
岡本 和久CFA
レポーター:赤堀 薫里
(この原稿は3月16日に開催されたFIWA®サロイン塾における岡本の講演を一部ご紹介するものです)
最近はつみたてNISAがきっかけとなったのでしょうか、投資に興味を持つ方も増えています。多くの方が始めたのだけれど、下がったらどうしよう?今なら少しもうかっているから売った方がいいのでは?トランプさん旋風で日本はどうなるか?物価上昇は?などいろいろな不安材料もあります。しかし、前回のサロイン塾でもお話したようにいろいろなニュースなどで売ったり買ったりするのは投機です。大切なのは投資です。そして将来のために投資という手段を使って資産を形成することです。
なぜ資産運用が必要か
「毎年の収入は今年の生活費と将来の生活費の両方であることを知る」、これは行動経済学者、ダン・アリエリ―さんの言葉です。例えばあなたが日当5,000円で月曜から金曜まで働くとします。毎日5,000円、使っていると土曜、日曜は一文無しで生活に困ります。ですから毎日、使う金額を3,500として1,500円を週末分にしておけば月曜から金曜で7,500円となり週末も一日3,500円で暮らしても少しお金が残る計算になります。人生についても同じこと、就業中の収入の一部は退職後のためにとっておくことが大切なのです。しかも、長寿化で退職後の生活は就業時と同じぐらいの長さになりつつあります。したがって、ただ「取っておく」だけでなく、「増やす」ことが大切になっているのです。
最大のリスクは生活の質の大幅な低下
私はあまり退職後のためにいくら必要という具体的数字は意味がないと思っています。第一に退職後の物価動向が不明です。重要なのは購買力です。第二にインフレに負けないよう資産を増やすには株式などリスク資産を持たねばならない、しかし、そうすると必ず資産価値は変動する。重要なのは、正しい資産運用を相場変動に関わりなく続けるということ。そして第三に人生の目的である「しあわせ持ちになること」は必ずしもお金に依存するものではないということです。今日は第一と第二を中心にお話します。
受験を考えてください。試験までにしっかりと受験勉強をして試験で最善を尽くす。あとは結果を受け入れるしかないのです。資産運用も同じです。若いうちから備えをしていき、退職時点が受験日。退職後はその資金を運用しつつ取り崩しつつ就業中に行った(あるいは行わなかった)ことの結果を受け入れねばなりません。とはいうものの路上生活者になるのもあまりうれしいことではありません。やはりあまりみじめな生活をするのはしあわせとは言えません。
では、退職後に抱える最大のリスクとはなんでしょう?お金がいくらあるとか、ないとかいうものではなく、それは就業中と比べて生活の質を大幅に下げなければならなくなるということです。その視点から資産運用を考えてみます。それは非常に簡単なことなのですが、それを実践する人がまだまだ少ない。まだまだ多くの人が売った、買ったでお小遣い稼ぎをするのが投資だと思っている。それは前回、お話したように投機です。大切なことは人生を通じて資産形成をすることです。
将来の自分を支えるのは今の自分しかいないのです。お国が助けてくれる、会社が面倒見てくれるという時代はずっと前に終わっているのです。できるだけ若い時から将来の自分を見据えて準備をしていくことが大切なのです。意識の時間軸を伸ばすことが大切です。
人生を会社や国に任せきりにするわけにはいかない。これまでの日本は「子供は親任せ、親は会社任せ、会社は国任せ、国はアメリカ任せ」それじゃこれからの(トランプ政権下の)厳しい現実に生き抜いていくのは難しいでしょう。国家も、産業・企業もそして個人も・・・。「自立」が今ほど大切な時はないでしょう。
時間を味方につける「72の法則」
もし、今の収入をほとんど今使ってしまうとリタイア後に確実に困ります。今は良いけれど将来は困る。これは当たり前です。
今の収入の半分使い、半分を将来のためにとっておくと、相当の高給取りでない限り生活水準は生涯を通じてかなり苦しい状態が続きます。とにかくずっと給料の半分で生活しなければならないのですから。しかもこれは名目ベースの話で、その期間の物価上昇の分が実質ベースでは目減りすることになります。
結論は、今の資金を将来のために増やす必要があるということです。説明を簡略にして就業中を通じての平均年収が100だとしましょう。30歳の人が資産運用を65歳まで行い、66歳からリタイア生活に入るとします。そうすると運用期間は36年ですね。この人は年収の7割、70を今の生活に使い、3割、30を将来のために運用します。
30歳の時に始めた資産運用の資金を66歳で使うとします。その後、毎年、一年ずつずらしていきます。31歳⇒67歳、32歳⇒68歳・・・・65歳⇒101歳。すべて運用期間は36年です。つまり収入の75%で生活する。そうすれば101歳までずっと36年ずつの長期投資ができることになります。
「72の法則」
どうしたらお金が増えるか。どれぐらい増えるか。金額はいくらでもいいのですが、分かりやすく例えば100万円を預金します。仮に金利が年3%としましょう。1年経てば3万円の利子がつきます。その3万円を毎年、使っていれば元本は100万円のままで増えません。しかし、この3万円を預金に追加していけば次の年は103万円の3%、3万900円の利子がもらえます。それをさらに元本に加えると106万900円の3%、3万1827円が利子になります。つまり、利子が元本に加わることで金利は変わらなくても預金額は増えていく。これが複利というものです。かのアインシュタインも「人類最大の発見は『複利の考え方』である」と言ったそうです。
時間を味方につけることは具体的には複利の効果を最大限、活用することです。その際に役立つのが利率×期間=72という組み合わせで資産額が倍になるという一般に「72の法則」と言われる数式です。例えば30歳から65歳まで36年あります。この間、毎年、2%ずつ投資収益が得られれば資産が倍になる。2×36=72ですからね。年4%だと18年間で資産が倍にということになります。
これから分ることは長く運用するほど元本が増えていうので低いリターンでも大きな効果が得られるということです。低いリターンということはよりリスクが低いということですから安全度も高い。これが「時間を味方につける」ということです。
大切なのは長期的な視野で考えること
面白いのは、日本で戦後株式取引が再開されたのが1949年5月です。その最初の第1日目の日経平均が176円でした。そして現在が約4万円になっている。非常に興味深いんですけれどもこの1949年5月、この日のニューヨークのダウ平均が176ドルなんですね。
そして現在はだいたい4万円対4万ドルということでほぼ同じ。要するに、日米ともに75年で200倍以上になっているということです。こういう視野で考える。そうすると今から75年後が、いつかというと2099年21世紀最後の年です。現在が約4万円として同じように200倍になっているとすると、日経平均とニューヨークダウが共に800万ドル、800万円になっている可能性だってあるということです。過去を振り返ってみれば戦争もあり、自然災害、ブームも経済危機も、大暴落もあり、いろいろな事が起こりました。これからも起こるでしょう。でも、そういうものを全部乗り越えて、日米の株式市場は値上がりをしてきたわけです。
戦後、株式取引が再開された1949年5月から2024年12月まで、日本の日経平均は年平均9.6%、アメリカのダウ平均は8.7%、ともに9~10%近くの上昇をしています。この値上がりをどうやってできるだけ少ない変動幅、ぶれ幅で獲得するかというのが長期資産運用のキモなのです。その簡単な方法をこの塾ではみなさんに学んでいただきます。
私が尊敬する長期投資のグル、ジョン・テンプルトンさんはこんな言葉を残しています。「21世紀が終わる頃にはダウ平均株価は現在の約1万ドルから100万ドルに達しているだろう。だから100年保有するつもりなら、目をつぶって株式投資をしても見通しは極めて明るい」とおっしゃっています。これは21世紀初頭のコメントです。(Sir John Marks Templeton, 1912年11月29日 – 2008年7月8日)
今回ご紹介したのは3月16日に開催したFIWA®サロイン塾の私の講演の一部です。講演全体はFacebookの「クラブ・インベストライフ」で公開しています。よろしければご覧ください。
(文責FIWA®)