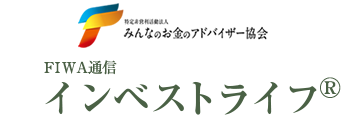【Vol.266】FIWAマンスリー・セミナ講演より(講演1)
⻑寿時代の最⼤の⽀え 公的年⾦の誤解と最⼤活⽤術
⽇本経済新聞社編集委員 ⽥村 正之⽒
NPO法⼈ みんなのお⾦のアドバイザー協会〜FIWAレポーター︓⾚堀 薫⾥
⽥村正之⽒ プロフィール
⽇本経済新聞社編集委員。証券アナリスト(CMA)、社会保険労務⼠、ファイナンシャルプランナー(CFP)の資格を持ち、年⾦など社会保障のフル活⽤と⻑期分散投資を組み合わせた総合的な資産形成術を発信している。著書に『⼈⽣100年時代の年⾦・イデコ・NISA戦略』『“税⾦ゼロ”の資産運⽤⾰命 つみたてNISA、イデコで超効率投資』など。⽥村優之の筆名で⼩説も執筆し、98年に開⾼健賞受賞。経済⼩説『⻘い約束』(原題「夏の光」で松本清張賞最終候補)は14万部を販売。
開催⽇時 2024年12⽉15⽇
これだけ⻑⽣きをするようになると、資産運⽤と同時に年⾦と社会保障もフル活⽤することが重要になってくるでしょう。誤解が多い年⾦の活⽤策についてお話します。
年⾦は、⾃分が今までこつこつ積み⽴ててきたものを後からもらう、貯蓄のようなイメージではなく、⼈⽣のリスクに備える保険です。法律の名前も厚⽣年⾦保険法であり、払っているのも保険料です。最も⼤きいリスクは、何歳まで⽣きるのかわからないということ。これに関しては、公的年⾦は死ぬまで⼀定のお⾦がもらえるという安⼼感があります。また、ケガや病気で働けなくなったときは障害年⾦、⼀家の⼤⿊柱が亡くなったとき⽥村正之⽒は遺族年⾦がもらえる⼈⽣のフルパッケージの保険です。逆に保険のため早死にしても遺族年⾦はありますが、本⼈がもらえる給付はありません。また今は、マクロ経済スライドで物価と賃⾦よりもやや削られることが多いのですが、基本的には物価や賃⾦に合わせて上昇してくれます。
⺠間の保険の場合、あらかじめ決まった保険⾦額は物価が上がっても増えません。しかし、年⾦は物価にある程度連動して増えてくれるため、インフレリスクにも備えられる仕組みです。⺠間でこういうものを作ると、現在払っている保険料よりもはるかに⾼い⾦額が必要となります。公的年⾦だからこそできるわけです。最⼤の機能は終⾝給付。65歳まで⽣きた場合、男性は4割ぐらい、⼥性だと6〜7割が90歳まで⽣きます。そして2割は100歳まで⽣きます。つまり⻑く⽣きるための⽣活設計が必要になります。そのためには⽣存中もらい続けることができる公的年⾦は最⼤のメリットとなるでしょう。
公的年⾦は2階建てです。1階部分は基礎年⾦。払い込むときは国⺠年⾦と呼ばれ、もらうときは基礎年⾦と名前が変わり、若⼲違いますがほぼ同じ意味です。基礎年⾦は40年払い込んだら定額で、今年度だと6万8000円もらえます。⼆⼈分だと13万6000円です。会社員や公務員の場合は、働いた⽣涯収⼊に応じて伸びたり縮んだりする厚⽣年⾦が加わります。平均的には男性の厚⽣年⾦は約9万円。基礎年⾦を合わせると16万円いくらです。そして妻の基礎年⾦を合わせると約23万円というのが今年度のモデル年⾦額です。
このモデル年⾦が、将来マクロ経済スライドでじりじり減っていくと⾔われています。しかしこのモデル年⾦は⽚働きです。今は共働きが⽚働きの3倍くらいになっています。⼥性も厚⽣年⾦があり、共に男性の平均収⼊のカップルが働いていると、⼥性も同額の厚⽣年⾦をもらえるため32万円くらいになります。⾼齢夫婦無職世帯の⽀出は、⼤体27〜28万円。共働きであればこれを超えてきます。年⾦は本来65歳からもらいますが、繰り下げると増えます。1ヶ⽉繰り下げるごとに0.7%増えるため、70歳まで繰り下げると42%増えます。今は最⼤75歳まで繰り下げられるため、そのときは84%まで増えます。そして繰り下げたものがずっと続きます。共に男性の平均収⼊で働いて、70歳まで繰り下げると46万円と、かなり⼤きな⾦額になります。
つまり働き⽅、もらい⽅次第だということです。逆に繰り上げてもらうこともできます。繰り上げてもらうと、1ヶ⽉繰り上げるごとに0.4%減るので5年繰り上げた場合は24%減。24%減った⾦額が⼀⽣続くわけです。もし、年⾦の受給を繰り下げた場合、繰り下げを待機している期間はもらえません。もらえない⾦額を繰り下げ待機後、もらい始めた増額でいつ取り戻せるのか。これは、もらい始めてから計算上11年11ヶ⽉で取り戻せます。つまり、70歳まで繰り下げると81歳11ヶ⽉でもらえなかった期間分取り戻せます。最⼤75歳まで繰り下げると86歳11⽉まで⽣きれば取り戻せるわけです。増額されているので、その後⻑⽣きすればするほど上回ってくるということです。
逆に繰り上げると、必ずもらい始めてから20年11ヶ⽉で本来65歳でもらうはずだった⾦額を下回っていきます。60歳まで繰り上げた場合は、80歳11⽉まで⽣きると65歳で本当は貰っておいた⽅が良かったよねということになるわけです。何歳で元が取れるかというのは、繰り下げの場合名⽬です。繰り下げて名⽬の⾦額が増えると税⾦や社会保険料も増えるため、⼿取りは名⽬ほど増えないケースがあります。税や社会保険料がどれくらい増えるかは、元の⾦額にもよります。例えば税や社会保険料が増えやすいのは、基礎年⾦と厚⽣年⾦を合わせた元の⾦額が200万円ぐらいです。元の⾦額が200万円ぐらいだと本来70歳まで繰り下げた場合42%増えるはずが31%しか増えません。税⾦や社会保険料でだいぶ減るわけですね。そうすると、元が取れる期間が、81歳11か⽉ではなく85歳9か⽉と遅くなります。
これは元の⾦額によります。例えば基礎年⾦だけで未加⼊期間もあった専業主婦の元の⾦額が70万円ぐらいの場合、元が少なくても社会保険料は頭割りで⼀定額取られるため、むしろ増え⽅が43%と若⼲ですが逆に多くなります。つまり専業主婦の⽅は繰り下げると⼿取りがほとんど減らさず、むしろ有利な額⾯がもらえるため、繰り下げは有利です。元の⾦額が240万円と多い⼈は、やはり税や社会保険料が⾷われるため36%ぐらい増えます。そうすると損益分岐年齢は83歳ちょっとになるわけです。
講演では年⾦のフル活⽤に向けた視点として、年⾦額は働き⽅、もらい⽅で千差万別であり、年⾦を「⾃分で育てる」⽅法を具体的な数値を基にわかりやすく説明。最後に年⾦財政については、正しく⼼配することの重要性を解説くださいました。
(⽂責 FIWA)