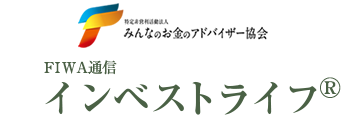【Vol.262】FIWAマンスリー・セミナーより(講演2)
三和 裕美子氏
明治大学商学部教授 博士(商学)
I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)代表取締役社長
レポーター 赤堀 薫里
大学卒業後、1988年から1991年まで野村證券岐阜支店に勤務。その後同志社大学アメリカ研究科修士課程、大阪市立大学大学院経営学研究科博士課程を経て、1996年より明治大学商学部および大学院にて「機関投資家論」を担当している。1996年から1998年には米ミシガン大学にて客員研究員を務める。
現在、全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員、地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員、ピジョン株式会社社外取締役、エーザイ株式会社社外取締役を務めている。著書多数。
投資家資本主義の未来 ―インベストメントチェーンにおける機関投資家の役割―
資産運用立国実現プランが進められています。その中で私たち個人投資家や機関投資家、それぞれが資本市場の中でどんな立ち位置にいて、インベストメントチェーンの中での機関投資家の役割というものを改めて考えてみたいと思います。
今、日本も含め世界の年金基金は、いろいろな資産を運用会社に委託して運用しています。非常に大きなプレゼンスをもっています。つまり労働者が生産手段を保有している時代です。私たちは、自分たちを株主という企業のオーナーとして自分の年金がどのように投資をされているのかを見ないといけないと思います。
GPIFもそうですが、ノルウェーの政府系ファンドの運用会社は、ポートフォリオの最適化の中で、一時的な、短期的な利益を追求するために非倫理的な行動をとるとか、または他の企業を犠牲にするといったようなことはしないと宣言しています。非常に責任ある長期的な投資家として、国民に説明し、国民の意見を取り入れながら運用しています。そのような方向で、GPIF も含めて私たちが企業の所有者だとオーナーだという意識改革をする必要があるのではないのかと思っています。
ノルウェーのNBIMアセットマネジメント会社は、ロンドンに事務所があります。世界中に投資を行っています。エンゲージメントといって、投資先企業との対話を非常に重視しています。昨今の関心としては気候変動についてです。非常に重要なことは、何をテーマにしてエンゲージメントするのかです。企業や学識経験者、市民団体などからの対話から情報を得て、対話設定をしています。
NGOや市民を招いてセミナーを開催して責任投資に関する取り組みについて議論していく。企業を変えていく、年金が企業にものを言う際のテーマとして市民、NGOといった最終受益者の意見を反映したエンゲージメントを行っているということが、日本にはないところです。例えば2022年は先住民の権利や環境、生物多様性、人権というテーマの中から特に鉱業セクターの課題を検討してここの産業に対してエンゲージメントを行っていることが特徴でした。
また、「我々にとってESGは政治ではなくて常識であり、良い投資判断を下すにはESGを考慮した分析を統合している。そして将来の世代のために富を築く」ということを明確にCEOのメッセージの中で伝えられているのが印象的でした。
インベストメントチェーンの中で、日本は、資産運用会社の改革も行い、アセットオーナーの改革も行いましたが、最終受益者が後回しにされているところがまだあるのではないのか。我々の最終受益者の意識を高める必要性がありますが、関心を持ってもらうためのシステム作りが必要です。我々の関心を、我々の意志を、エンゲージメントに反映させていくというところまで目指していく必要があると思います。
例えば、私は全国市町村または地方職員共済組合の年金の運用委員をやっていますが、GPIFほど大きくありませんが、アセットオーナーの改革として取り組んでいるのが、最終受益者に対して議決権の状況やエンゲージメントの状況をどのように報告するのかというところです。
それは一枚の新聞のような「このようにアセットマネジメント会社と対話をしました。今回のエンゲージメントはこのようなテーマでアセットマネジメント会社は行っています」という報告書を、各自治体に配布しています。しかし日本の場合、配布しても年金の最終受益者は見ないことが多い、その程度のレベルです。そこのところを大きく意識改革とシステム作りをしていく必要があると思います。
ケイレビューのジョン・ケイさんの話ですが、「金融に未来はあるのか」という答えとして、ロバートシラーが「金融は、リスクを管理するだけでなくて、社会の資産の管理保全者として機能して、社会の最も深い目標を支援する存在となる。そのためには金融の便益を最も必要とされる社会の隅々にまで広げていく。それが新世代にとっての課題だ」と言っています。
まさに、金融というものの役割を発行体の資金調達という役割だけを見るのではなくて資産の管理保全者として、最も深い目標を支援する存在であるというところが将来的に金融に私たちが認める役割なのだと思います。その鍵となるのは資産運用会社などの機関投資家です。インベストメントチェーンの中の機関投資家と、お金の出し手である最終受益者である我々個人投資家です。
個人投資家が能動的に企業や、社会、地球温暖化の変革に促進する主体として関与する、意識することが今後の金融にとって重要ではないのかと思います。現状は個別企業の事業ポートフォリオや資本政策については、アクティブファンドやアクティビストとかのエンゲージメントによって変革がもたらされる。今ももたらされている状況です。問題として、最終受益者は機関投資家をモニタリングする立場にありますが、それだけのリテラシーが必要です。機関投資家が企業をモニタリングする。このインベストメントチェーンを構築するということは、日本の状況にとっても大きな課題かなと思います。
講演では、金融経済の肥大化と投資家資本主義、インベストメントチェーンにおける機関投資家の役割、ユニバーサルオーナーシップ論、機関投資家のエンゲージメント事例について、また、株主アクティビストの活動について大変興味深い解説をいただきました。
(文責FIWA)