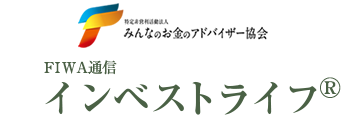【Vol.258】FIWAマンスリー・セミナ講演より(講演1)
日本における株主アクティビズムとコーポレートガバナンス
明治大学商学部教授
I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社
代表取締役 社長 三和 裕美子氏
レポーター:赤堀 薫里
三和 裕美子氏 プロフィール
1965年生まれ。
現在 明治大学商学部教授 博士(商学)。
大学卒業後、1988年から1991年まで野村證券岐阜支店に勤務。その後同志社大学アメリカ研究科修士課程、大阪市立大学大学院経営学研究科博士課程を経て、1996年より明治大学商学部および大学院にて「機関投資家論」を担当している。1996年から1998年には米ミシガン大学にて客員研究員を務める。
現在、全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員、地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員、ピジョン株式会社社外取締役、エーザイ株式会社社外取締役を務めている。
主な研究分野は、機関投資家とコーポレートガバナンス、機関投資家のエンゲージメントとESG投資、資本市場と女性活躍、アクティビストが企業に及ぼす影響などであり、関連論文を多数公表している。
主な著書として、『機関投資家の発展とコーポレート・ガバナンス』、日本評論社(1996年)、Corporate Governance in Japan(共著)、シュプリンガーフェアラーク東京(2006年)、『東アジアとアセアン諸国のコーポレート・ガバナンス』(編著)、税務経理協会(2016年)、『図説 企業の論点』(共編著)、旬報社(2021年)、『激動の資本市場を駆け抜けた女たち』白桃書房(2022年)、『ファイナンス入門』(共著)、ミネルバ書房(2021年)、『DXと人的資本』(共著)、税務経理協会(2023年)、投資家資本主義の未来(新刊)千倉書房などがある。
日本における株主アクティビズムとコーポレートガバナンスというタイトルでお話をします。アクティビストたちの活動が非常に最近活発になってきています。東証のPBR改善要請も含めて、それがかなりアクティビストの後押しとなり、2023年ですと、アクティビストのいわゆるキャンペーンが340件ぐらい、株主提案で90件ぐらいというような数字になっています。今年はもっと多くなるのではないかと言われています。それとガバナンスとどう考えるのかをご紹介します。
コーポレートガバナンスシステムと私は名付けていますが、狭義のコーポレートのガバナンスとは、株主と株式市場による株価の評価を通しての株式会社へのチェックシステムと解釈されます。
しかし、制度として株式会社を見ることを、1930年代にバーリー・ミンズのバーリーと法律学者のドットが論争を行っています。その制度としての株式会社と捉えると、株式会社は、株主だけではなくて、従業員、債権者、地域あるいは取引先といろいろな契約に基づいた関係性を構築しているわけであり、それぞれの立場から株式会社の行動あるいは経営者の行動を牽制できる仕組みを持っている。
例えば従業員であれば労働組合とか。債権者であれば債権、融資によるモニタリングといったところですが、なぜ株主だけが株主価値最大化と言って、特別視されるのか。その理由は、株式市場なのです。株価による評価。株式市場が効率的になればなるほど、非常に全ての情報が株価に織り込まれていき、その株価によるモニタリングが瞬時に働く。なおかつ従業員や債権者、その他取引先の牽制システムというのは、それぞれに従業員、債権者がいますので、すべての企業は同じように評価をすることは難しい。ところが株式市場というのは投資家が同じ基準で評価をするわけです。
株式市場が最も効率的市場になればなるほど、株式会社のシステムの中で最も効率的また合理的に株式会社を牽制できるという考え方です。
確かに株式市場の評価、株価の評価というのは、世界のアナリストやファンドマネジャーが、どこの国にいても同じような方法で評価しますので、そういった意味では最も合理的であるということで、株式、株価によるガバナンスチェックが今まで考えられてきました。
ただ2019年、アメリカのビジネスラウンドテーブルのガバナンスの解釈の変更で、ステークホルダー、マルチステークホルダー主義と、その他のステークホルダーも含めてガバナンスというのは考えなきゃいけないんだ、ということになっています。
これはもう既に30年代にドットが言っていますが、環境が変わっていくと、株式市場の評価の性能というのも上がっていきます。しかし、社会が変われば社会からの見方というのも自ずと培われていくため、制度として株式会社を考えるという考え方は、将来これがもっともっと大きくなるだろうと30年代にアメリカで予測されていました。
しかし、2019年まで、ビジネスラウンドテーブルの考え方の変換まで、株式会社は株価による評価、あるいは株主価値極大化というのがアメリカでは通説でした。今は世界的に見て株価が最もイコール的ではあるけれども、他の牽制手段もあるよね、というようなものがガバナンスシステムの大枠だと考えてください。
あるアクティビストさんがインタビューで「なぜアクティビストがアクティビスト活動を行って株式会社に関与していくのかというと、株主による評価、株価による評価というのが他の債権者や、他の従業員に比べても最も合理的ではある。なので、アクティビストがアクティブファンドとかアクティビストが会社経営に関与していくことが、他のステークホルダーにとっても良いことであり合理的だった」というようなことをおっしゃっていました。
ちょっと話は変わりまして、コーポレートガバナンスの今の現時点。あるいはコーポレートガバナンス改革の現時点の評価はどうなのかといったときに、まず、コーポレートガバナンス改革、企業統治改革とは何だったのか。アベノミクスのビジョンで3本の矢とか成長戦略の中核となったのが、コーポレートガバナンス改革でした。
その問題意識としては、日本企業は世界的にROEが低すぎる。いわゆる稼ぐ力がない、リスクテイクもしない。ここを変えないと国際的な競争力に勝っていけないということで、経営者のマインドセットを変える。つまりこれがガバナンスの主要な問題です。そして今は社外取締役が積極的にリスクをとって経営できるようにアドバイスもしくは監督する、ということになっています。それから内部留保が多すぎるといったところです。これを促進していくことによって持続的な成長が促され、結果的に従業員に雫が落ちる。トリクルダウンは落ちるよねっていうようなビジョンがありました。
講演では、コーポレートガバナンス改革について、そしてボード(取締役会)の歴史をひもとき、今までのボード1.0、ボード2.0について、またアクティビストがボードに入るボード3.0とそれぞれの考え方の違いや背景について説明。最後に、株主、アクティビストが日本企業にどのような影響を与えているのか解説くださいました。
(文責FIWA®)
Free Discussion
参加者|三和先生は、社外取締役をピジョンとエーザイでされていらっしゃいますよね。株価と株価の面から見た企業価値に関してどういう認識、議論をされているのか感想をお伺いしたいです。質問の背景は、私が持っている銘柄の6月の株主総会で質問をしようと思っています。その会社はプライム市場上場で、ここ4~5年、ちょっと中国の比率が高いということで業績も伸び悩んでいて、特に株価に関して言うと、この2年ぐらいで半値以下になっています。TOPIX比較ではかなり悪い。その前は急成長していました。
そういう中で、例えば先生がお話しされていらっしゃるピジョン。ピジョンは中国比率が今約3分の1まで下がってきました。でも株価はこの5年、6年、ピーク時から6分の1、5分の1。ピジョンはいわゆる非常に先進的な会社の一つかなと。取締役においても。でも株価はここ4~5年、誰が客観的に見ても企業価値は下がっていると言わざるを得ません。株式市場、投資家からしたらそう判断せざるを得ないですね。
3月の総会で、「いくら会社としてやっています」と言っても、市場からの評価が正直真逆です。上場来安値を更新しているような中で、社外取締役と経営者の人たちは株主に対してどのようなプレッシャーを感じて、株価に対して意識を持っているのか。株価は市場が決めることだから仕方ありません。今は頑張って事業改革をやりますということなのか。それとももう少し資本コストと株価を意識した経営が求められている中で、これだけ株価のパフォーマンスが急落している時に、取締役会の内部でどのような議論があるのか。私が持っている会社はピジョンとは違いますが、非常に中国依存比率が高くて偶然とはいえちょっと近いので、三和さんの意見をお伺いしたいです。
三和|おっしゃるように、昨今、株価全体が上がっている中で安くなっていると、非常に厳しいです。株主総会では個人株主さんはすごく厳しい。今のような「どう考えているんだ!経営人は!」というような質問もあります。株主総会に議決権も既に票が集まっていますけど、ちゃんと株主総会が機能しているなと感じます。
それを株主総会でガーンと言われて、もちろん今の時代、株価は市場が決めるなんて絶対通用しません。そんなことを言おうものならいつの時代だと私は思います。そんな経営者は多分いるのかな?認められないと思います。それで、今の株価をどのように見ているのか、なぜこの株価なのかというのを業績、マクロ的な外部環境、地政学的なリスクをちゃんと客観的に示し、そして将来ビジョン、中長期ビジョンをどういう戦略で持っていくのかみたいなことをきちんと経営者や我々社外も含めて説明できないと信頼されないですよね。株主総会等で厳しいお言葉をいただいて、やっぱりプレッシャーがかかります。
社長も含めて取締役のメンバーは本当になんとかしなきゃいけないというようなプレッシャーはもともとありますけど、個人投資家にガーンと言われるとね。個人投資家さんお話が上手くて「私はピジョンの製品をずっと使っている。ずっと株主なんだけど全然ダメです」みたいなことを言われると、身につまされ感が伝わってくるので、株主総会の発言は、ぜひしていただいたほうがいいと思います。
ピジョンは、赤ちゃんとお母さんさんに優しいというビジョンを掲げているのですが、そういう存在意義、存在価値は、直接株価で反映されません。そこの価値評価を、AIが発達してくる中でソーシャルインパクトの定量化があと数年くらいで出てくるんじゃないのかなと期待はしています。
岡本|そうかもしれないですね。やはり株式市場にそういう存在意義というのか、存在価値みたいなものがもっと反映される。それはある意味、証券アナリストとか株価形成に一役買っているような人たちの価値観の問題という部分はあると思います。
三和|そうですね。アメリカの登山とかの服を作っているパタゴニアという会社があります。社会的企業と呼ばれている会社ですが、そういうところを若い方はより好む傾向にあるんじゃないかなと思います。
岡本|なるほどね。そこの株式市場というものの価格形成がもう少し進化してもいいのかなと思います。要するにファンドマネジャーやアナリスト自身が非常に短期的になっていて、取りあえずすぐ儲かるものを中心に買っていかなきゃいけない。競争に残れないみたいな。解約されちゃう。
そっちの方の話が優先して、どうしても特に対インデックスで戦っているとなると、やはりマーケットについていくのは当たり前で、さらにそれを上回っていかなきゃいけないという使命を帯びていると、そこがなかなかこの会社が、長期的に社会のために本当に役立っていて、それがどれくらいの評価の基準の比率になるのかというのは難しいところですよね。
三和|私は考えたんですけど、例えばピジョンは哺乳瓶作っていますよね。お母さんは母乳だと自分が拘束されるでしょ。私は子供が0歳から保育園に哺乳瓶と預けていました。哺乳瓶があるからこそ私も仕事に行けるわけじゃないですか。ある計算だと、例えばその哺乳瓶でお母さん以外の人が授乳をするその回数や時間は、1年間にその時間をお母さんが家事労働もしくは一般労働で振り分けると考えたときに、数値化でこれぐらいのインパクトを生み出しているんだ。
哺乳瓶によってお母さんの女性活躍のインパクトはこうですというものが言えます。でもそれは言ったもの勝ちみたいなところがあり、横並びで比較できるものではないので、そういうことは難しいです。しかし、徐々に企業さんはそういうものが社会的なインパクトとして数値化できるようにと少しずつやっています。
岡本|そうですよね。やっぱりそういう部分がもっと出てくるといいなと思いますね。
三和|そしたら、将来キャッシュフローに社会的インパクトを入れて割り引いたら株価は下がるのではないのかとか思ったりします。
岡本|やっぱり世の中を良くしていくというのがミッションなわけですよ。あらゆる企業もあらゆる個人もね。多分そうだと思います。だからそれに沿ったような形で株式市場が評価をするようになったらいいな。
私は、今の証券アナリストの中ですごく欠けていると思うのは、利益の質という問題です。例えば一株いくら稼いでいる。その「稼いでいる」は、どこでどういう風に稼いでいる、どういう思いで稼いでいるのかというね。質の良い利益なのか、質の悪い利益なのか。
これは今からもう相当昔の話ですが、80年代ぐらいにCFAの試験をやっていた時にすごく出てきた言葉で、Quality of earningsという、利益の質というものをすごく重視していました。でもそれは結局、進化した形、もしくは複雑化したのかもしれないけど、ESGなんかと同じような部分もあるわけですよね。はい、今日もありがとうございました。
(文責FIWA®)