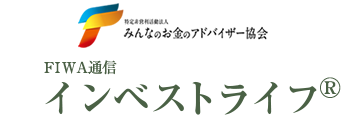【Vol.239】FIWA認定会員 投稿コーナー
内田英子(CFP,FIWA*)さんのブログより「適切なつみたて投資の家計への組み入れ」
*FIWAは金融商品の販売を行わないアドバイザーに与えられる称号です
今号よりFIWA認定会員の方の投稿をご紹介するコーナーを掲載します。
全五回のうち今回は三回目の内田英子さん、松山で活躍しているホンモノのアドバイザーです。
寄稿:FIWA®協認定正会員 内田 英子 氏
CFP、FP1級、消費生活アドバイザー
FPオフィス幸せ家族ラボ代表。
証券会社、保険ショップ勤務を経て、独立。
かつての専業主婦経験も活かしながら、子育て世帯を中心に家計の総合医として暮らしの健康を維持するあらゆる選択のアドバイスを金融機関から完全に独立した立場で行っている。
HP:https://fplabo-happyfamily.com/
Instagram:https://www.instagram.com/eiko_fp/
②iDeCoを優先するケース
こんにちは。FIWA®正会員の内田英子です。
前回に引き続き、テーマはつみたて投資です。前回のコラムでは私がお引き受けした家計相談の現場において、つみたて投資を使った資産形成でつみたてNISAを優先するケースについてご紹介しました。今回のコラムでは、iDeCoを優先したケースについてご紹介します。皆様の資産形成やそのアドバイスにお役立ていただけましたら幸いです。
◆ご相談者データ
Bさん(38歳・会社員)、妻(39歳・会社員)、長女(小5)、長男(小1)
愛媛県在住
◆ご相談内容
中古住宅を購入後、9年が経過。今後リフォームも必要になると思われるため、家計のことが気になってきた。今後の生活設計についてアドバイスが欲しい。つみたて投資は一切やっていないが、よく聞くためやった方がいいのかも気になっている。
◆ご相談時のBさん夫婦の希望と将来の見解
- 教育:こどもは2人。2人とも高校まで公立で、大学は2人とも県外の私立文系を想定している。仕送り額は平均額を見込む。
- 住宅:一戸建てを保有。住宅ローンは夫のみ契約。11年目以降金利が変わる段階金利を利用している。翌々年以降、返済額が上昇する見込み。返済期間は35年で世帯主63歳まで。
- 働き方:夫婦とも今後の職に不安はないが、昇給は見込めないと思っている。
- 生活:家計管理は妻が担っており、貯蓄を確保している。教育費に不安がある。保険も複数加入しており、加入内容についても見直したい。
- つみたて投資は行っておらず、できれば怖さもあり進んでやりたくはない。でも関心はある。
- 老後:できる限り働き続けたい。介護や療養が必要な場合は自宅での介護療養を希望する。
◆Bさんの家計データ
- 年間収支 約198万円
- 年間世帯収入計 970万円
- 夫 年収(給与収入・額面)520万円
- 妻 年収(給与収入・額面)450万円
- いずれも65歳退職。退職金は見込まない。
- 児童手当 年24万円
- 金融資産計 約1,210万円
- 預貯金 約1,000万円
- 保険(積立型)約210万円
【1】楽観的にみれば生涯資金が尽きることはない見込み
夫婦共働きで頑張っていらっしゃるBさんご夫婦。
お子様の教育に熱心で教育費は高い水準でしたが、基本的な生活費を低く抑えるめりはりの効いた堅実な家計管理で、しっかりと貯蓄ペースを維持していらっしゃいます。今後のリフォームを検討し始めたのを契機に、ご相談にいらっしゃいました。老後生活を見通して、家計の在り方について見直したいとのことでしたので、ライフプランシミュレーションを実施して現状の家計分析を行いました。
その結果、まとまった資金のリフォームを複数回こなしながらも年1%物価上昇を想定すれば、今後年収が上がらなくとも65歳退職後も生涯資金は尽きることはないことが見込まれました。ただし、万が一の際に必要と見込まれる保障額は最大で2,000万円程度不足していることがわかりました。
しかし保障を増やすとその分保険料負担は増加します。そこで、まずは現在加入している医療保険の見直しとともに、死亡保障の積み増しにより保険料負担を抑えつつ保険を見直す方法についてご提案しました。
【2】厳しい見通しを盛り込めば、老後資金は枯渇する可能性
物価上昇年1%を見込めば問題のないBさん世帯でしたが、今後の一層の物価上昇と年金手取りの目減りを見込めば80歳頃に資金が枯渇する可能性が見込まれました。現在の経済情勢を踏まえると物価上昇と年金手取り減少への対策は家計にも盛り込んでいきたいところです。
そこで、以下の2つのご提案を行いました。
- 家計を改めて振り返り、無駄な支出を見直しつつ、やりくりを引き続き意識すること。
- iDeCoに夫婦で加入し、お金の置き場所を変えること。
リスクを取った資産形成には抵抗のあったBさん。つみたてNISAのラインナップでは投資信託のみとなっているため、特に心理的なハードルが高いようでした。
そこで、ラインナップに定期預金などの元本保証の金融商品も含むiDeCoをご提案しました。最近は金融機関によってはiDeCoのラインナップから定期預金を外しているところもありますが、まだ残っている金融機関もあります。今後はなくなる可能性があることやiDeCoでの運用を定期預金でする際の注意点、また金融商品のリスクについての考え方もじっくりと一緒に確認していきました。
その上でiDeCoについての詳しい内容とBさんの世帯に当てはめた掛金拠出による節税メリットが理解できると、資産形成へのハードルは少し下がったようでした。
ちなみに、Bさん世帯はご夫婦共働きであり、ライフプランシミュレーションでは昇給は見込んでいませんでしたが、今後は昇給の可能性がもちろんあります。そこで気掛かりなのは、高等学校等就学支援金制度の足切りにあわないかという点でした。
現状の世帯年収から、おそらく足切りにあう可能性は低いだろうと思われましたが、その点でもiDeCo活用が適切と思われました。iDeCoへの拠出を行うことによって、足切りとなるボーダーラインを遠ざけることができるためです。
【3】未来の自分に選択肢を残しつつリスクにより強い家計に
iDeCoや金融商品のリスクへの理解の深まりとともに、リスクを取った運用へのハードルが下がったBさん。定期預金を含んだポートフォリオをご自身でつくり、ご夫婦合わせて年間48万円、iDeCoでの運用を始めることとなりました。
幸いBさんはご夫婦共働きでそれぞれの年金がしっかりあり、家計管理の意識も強くできるかぎり長く働きたいというお考えもお持ちでした。これらの強みを生かせば年金の繰り下げや世帯収入をできる限り維持するための選択肢も残されています。
こういった様々な状況から、これからの物価上昇や年金手取り減少のリスクを見込んでも年2%程度の利回りを想定したリスクを抑えたポートフォリオで対応していけるのではないかとの見込みが立てられました。
また、夫のみで住宅ローンを契約していましたが、妻万が一の保障は一馬力になるにも関わらず住宅ローン返済負担を加味しないままでした。今回の保険の見直しによる無理のない保障の積み増しで万が一にも強い家計となりました。
【4】まとめ
つみたて投資においてiDeCoを優先した事例をご紹介しました。
今後の社会状況を見込めばまだまだ不確定要素はありますが、まずはご自身の望む一生涯の暮らしのために今からできることを一つでも多く見つけることが大切です。そしてその選択肢は案外多くあります。
そのためには長期的、そして総合的に生涯の家計を見て合理的な判断を行うことが欠かせません。
一方で合理的な判断をお一人で行うことは必ずしも容易ではありません。
利益相反のないアドバイスの役割について実感し、改めて気持ちが引き締まる想いです。