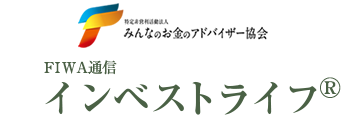【Vol.259】FIWA特別イベント特集
NISAで踏み出そう長期積立投資 手に入れよう経済的自立
資産運用立国への歩みが始まった
登壇者:金融庁総合政策局政策課金融税制調整官 今井 利友氏
なかのアセットマネジメント代表取締役社長 中野 晴啓氏
FIWA代表理事 会長 岡本 和久
コーディネーター FIWA代表理事 理事長 岩城 みずほ
司会 このセッションのご登壇者を紹介させていただきます。
最初に金融庁総合政策局総合政策課、金融税制調整官の今井利友様です。今井様は国税局で10年勤務された後、金融庁へ異動し、税労経験から新NISAの制度設計まで広く推進されています。今井様、本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。
続いてなかのアセットマネジメント代表取締役社長の中野晴啓様です。中野様は2006年、セゾン投信株式会社を設立、代表取締役社長、代表取締役会長、CEOを経て、2023年6月に退任。現在はなかのアセットマネジメント株式会社を設立し、積立・長期・分散投資による顧客本位の資産形成の第一人者として知られていらっしゃいます。本日は中野さんよろしくお願いいたします。
FIWA®の代表理事 会長の岡本和久です。よろしくお願いいたします。また、コーディネーターを務めますのは、代表理事 理事長の岩城みずほです。FIWA®認定正会員として相談業務を行うほか、一般社団法人 みんなの金融金融教育協会 代表理事として、大学での金融教育や、企業への投資・資産運用教育を行っております。それでは岩城さんよろしくお願いいたします。
岩城 みずほ これから、皆さんとパネル・ディスカッションを始めたいと思います。まずは私の方から3人に1人1~2問ずつご質問をします。最初に今井さん、認可の拡充、本当に素晴らしい改革でした。一個人投資家としても本当に心から感謝しています。非常に好評でして、口座数も着実に伸びている。まずはその状況をご覧になって、どういうご感想を持っていらっしゃるかということを一つ伺いたい。もう一つは私から質問なんですけれども、NISAというのは、生活者が長期で積み立てをしていったり資産運用をしていくための家計口座として非常に貴重な大切なお金の置き場所だと思うんですね。個人的には、積み立て認可を拡充していただいたのでも良かったんじゃないかなという気持ちもあるんですね。成長投資枠の方では、さまざまな運用商品を買いますけれども、中には長期投資に必ずしもそぐわないものというのもあるような気がします。例えば隔月の分配型の投資信託であるとか、そういったものはラインナップに入ったりとか、そういうのも投資対象になるかというその理由を伺いたいなと思っております。
今井 利友氏 最近、日銀から発表された資金循環統計がニュースでも出ております。けれども、株投資の割合が非常に伸びているということで、1年間で全体で2,053兆円が2,199兆円になっているんですけれども、株と投資信託がそれぞれ30%強増えているということです。我々もともとNISAを始めたとき、この預金が日本はすごい偏りが大きくて、ドイツとかアメリカとか株式投資信託の比率が高いんですけれども、日本はちょっと低すぎるのではないか、ということで、これを増やしていきましょうといろいろミッションをやってきたということなんですけれども、1年間で33%とかなり増えているということで、動かない山が動き始めたかなという感じです。喜んでいたら、実はTOPIXが1年間で30%くらい増えているんですね。ほとんどは株価のおかげという意味なんですけれども、投信の方も確実に資金の方も入ってきておりますので、やはり少しずつ山は動いてきているのかなと思っていますので、まずは良いスタートが切れたかな、と思っております。
それから2つ目の質問ですが、積み立てだけにしただけでもよかったのではないかという声もあるのですけれどもやはりこれある程度、自由度を与えてほしいという意見もありました。もし積み立てだけだと、例えば退職期などまとまったお金が入ってきたときにNISAを活用するのに積み立てでやらなきゃいけなくなる。「50歳から積み立てるの大変ですね」みたいな話があるので、そういったまとまったお金をもらう方にも使いやすい制度にしなければいけないというのが1つです。
それから、これは資産運用倍増プランの1つなんですね。その他にも、今日はいろいろと機構の話も出ると思いますけど、アドバイザーの話などいろいろなプランとしてやりましょうということなので、NISAだけで全部やるという話ではありません。そうすると、どういった投資商品がいいですかというと限界があってですね。例えば、昨年毎月分配がちょっとひどいんじゃないかということで規制したら、当時はなかった隔月ならいいんじゃないかという話が出てきたわけですよね。隔月も禁止してくれみたいな話もあるんですけど、隔月を禁止したら3ヶ月に1回ならいいのかって話になる。どんどんやっていくと、結局、分配金があるファンドを12ヶ月買ったら毎月分配と同じじゃないかみたいな話になって、これ、キリがないんですね。制度などある程度、そこは制度として決める部分と、それから金融業、アドバイザー、そういったところでサポートしていくという部分で、両輪でやらなきゃいけないということになる。制度としては毎月はダメというふうに決めているということになります。
岩城 みずほ 続きまして、岡本さんに質問させていただきます。NISAの拡充、そしてeMAXIS slim、オールカントリーのような低コストで全世界の主要な株式に投資ができる投資商品ができて、本当に生活者にとっては資産形成をしやすい環境ができてきたと思うんですね。ただ、この10年というのは、アメリカを中心に非常に投資リターンがいい時期であって、そして今後、平均への回帰が起こるのが自然であるというような話もあります。岡本さんに積み立て投資、長期投資ということの意義を参加者の皆さんにメッセージとしてお願いします。
岡本 和久 一部のインデックス型の投資信託などが非常に大きな人気を集めて、みんなそれさえ買っていいでしょうみたいな感じになってきたんだけど、まあ、その個別のファンドがどうなるかというのは今、私がここで話すことでもないし、また事実、よくわかりません。また、マーケットがどうなるかという予測も私はしません。予測をしないで済むような運用をしていればいいのです。けれども、インデックスファンドというのは規模が大きくなるほど運用も楽になってくる。トラッキングエラーが小さくなる。品質そのものが向上していくわけですよね。アクティブと違って銘柄を増やしていかなければいけないという、そういう難しさもない。信託報酬も安い。
その意味ではね、信託報酬が下がってくると、さらに資産も増加していい循環に入っていくということはあると思います。ただ一方でね、やはり規模を増やしたいために運用報酬を下げていくということになっていくと、今度は資産1単位あたりの収益性はどんどん下がっていくわけですよね。やっぱり後発組なんかは追いかけの値下げ競争になってくるんです。私は90年代に年金運用をしていましたけど、まさにあの当時、年金でのインデックス運用というのは盛んに出てきた時代でして、同じようなことが今、個人の世界でも起こりつつあるのかな、というふうに思っています。
でもそうなってくるとね、運用会社として果たしてこのファンドはビジネスとして意味があるのかという疑問は出てくると思います。また多くの投信会社は金融機関が親会社として保有しているケースが多いですから、そういったところは自分たちの株主に対する経営責任がありますから、簡単に今は儲からないがこれは大事なファンドだからって、そこのところだけを見て続けるのも難しくなってくる。そういう意味でやっぱりこんなに儲からないのか、「ちょっと考え直さないといけないね」っていう議論も当然出てくるだろうと思うんですね。だから私はこれから重要なのは長期投資のためにはファンドの持続性、ファンドがずっと続くという点だと思っています。インデックスファンドであっても、それを選ぶときにそこをよく考えた方がいい。本当は人生を通じてやっていこうと思っているのに、5年経ったらなくなっちゃいましたでは困る。それはまさに運用会社とその保有者のも含めてのファンドへのコミットメントだと思うんですね。やっぱりこれから運用会社の所有形態がすごく、私は重要になってくるんじゃないかと思います。
それから、アクティブの方もインデックスとの運用に競争に常に晒されているわけですよね。アクティブ運用をやっているファンドを全部集めると市場全体になるんだけれども、パフォーマンスは市場より必ず下がります。それはアクティブの運用報酬はインデックスよりも高いからパフォーマンスその分、下がる。アクティブは全体としてみれば必ずインデックス全体には負ける。つまりマイナス・サムの世界です。そういうマイナス・サムの世界でどうやって生き延びていくか、それはしっかりした投資スタイル、投資哲学を持って、そこからブレずに運用していく。投資家はその運用スタイルを買うというやり方に変わってくるだろうと思います。
長期投資の意義という話ですが、行動経済学者ダン・アリエリーさんが「毎年の収入は今年の生活費と将来の生活費の両方であることを知るべきだ」ということを言っています。今もらっている給料を全部使っていると、将来必ず困ります。老後もらえる年金だけで生活が成り立つのは非常に難しい。だから、とにかく今の収入の一部分は将来のために取っておく必要がある。貯金箱に入れて取っておくとしても相当大きな金額を取って置かなければならない。そうすると今の生活が難しくなってしまう。だから、やっぱりそれを少しずつでも増やしていく努力が必要だということですね。これが資産運用が必要な理由です。
要するに、将来の自分は今の自分しか支えてくれる人はいないわけですで、就業中にできる限り準備をしておいて、退職後にはその成果をうまく使いながら、その時自分が持っている資産で自分の幸福感を最大化できるようにすればいい。そういう意味では私は「75文字の資産形成」をいつも言っています。簡単に説明すれば若いうちから前年の収入の一定比率、例えば前の年360万もらったら、例えば20%、72万円ですね、それを12等分して毎月6万円積み立て投資をする。そして、とにかく持続性のある質の良い全世界の株式インデックスファンドに積み立て投資をする。相場変動に関わらずそれをリタイアするまで絶対にやめない。
それだけですよね。これだけやっていれば多分そこそこ達成できると思います。始めなければ何も起こらない。そして、続けなければ結果は出ない。だから「始める」ことと「続ける」こと、長期分散積み立てっていうのはこの2つが最重要ですね。
長期、分散、積立などが長期投資成功の重要な項目といいます。まあ、それは本当なんですが、私はあと2つ、継続と資金流出の最小化が大切だと思っています。運用ってものすごい資金が流出しています。いろんな形で、例えば自分のライフプランに全然合ってないような投資信託を持っていること自体、無駄な資金が流出している。それから必要のない売買をするとかね、無駄な資金の流出を一切省く。バケツの底に穴が開いてるならそれはとにかく塞がなくてはいけない。
それから積み立て投資をしいてるのに途中でちょっと休むのも問題です。ちょっと下がると「取りあえず休もう」というのは危ない。「休むも相場」と言うけどそんなことはない。いつ休んだらいいかなんて誰にもわかるわけない。とにかくずっと続ける。要するに継続が大事。
資金流出の最小化、つまりバケツの穴を塞ぐ防ぐために重要なのは、私は金融商品を一切販売をしないFIWA®のようなね、アドバイザーを伴走者として使うことだと思います。伴走者ですから前に出て走っちゃいけない。主役のランナーが変な方向に行きそうになったらちょっと教えてあげる。それが大事なんですよね。そういう立場の人がこれからすごく重要だと思いますし、また欧米などではね、アドバイザーは一つの職業として成り立っているということを感じます。
岩城 みずほ 続きまして、中野さんよろしくお願いします。非常にインデックスファンドが売れまくっている中で、あえて中野さんは世界成長ファンド、日本成長ファンドと日本のアクティブファンドを作られました。その理由についてと長期保有をしていただくためにどのようにして共感を得ていこうと考えていらっしゃるか。その辺りをお話しください。
中野晴啓氏 中野でございます。今日6月末ですよね。ちょうど1年前には私は前の会社を退任しましたので本当に1年ぶりです。1年前は一番しょぼくれた人でしたが、すっかり元気になりました。それで新しい会社を立ち上げて今ご質問いただいたように、僕は「ド」アクティブの運用会社と言っています。何より一番の理由は、世の中の環境というのが今一番僕の心を突き動かしている変化ですね。
これは僕のセゾン投信をやった時代からの問題意識です。ここ数年、日本の資産運用業界に本格的なアクティブ運用がきちんと定着しないと感じてきました。これからは資産運用の高度化といってもタワゴトで終わってしまうぞと思っておりました。それについて前の会社でも方向を変えていかなきゃと思って、一つ一つ準備をして動き始めたところだったんです。しかし、途中で追い出されちゃいました。
今回、ゼロからリセットで立ち上げることができる機会をいただいたので現在の社会的需要に鑑みて理想とする運用会社を作ろうと思った。これが最大の理由です。実はさっきずっと画面を見ていて、それから澤上さんと岡本さんの対談を見ていて投資ルネッサンス宣言が紹介されていましたが、僕はあの時、2007年1月でしたよね、セゾン投信を1月に運用開始するということで、もう準備をすべてして、あの中の聴衆の1人だったわけです。懇親会では、動画に出ていた方々に囲まれて、お前どういう運用をするのか言ってみろなどと議論をふっかけらりたり、期待されたり、挑発されたりしたのを覚えています。
実は動画で紹介されていた五カ条の個人投資家宣言、これって今、本当に必要とされている事そのもので、まさにあれこそ金融庁が言っているインベストメントチェーンなんですよ。英語になっただけ。インベストメントチェーンの理想のサイクルっていうのは、まさにあの五カ条の宣言です。澤上さんは当時の相場の雰囲気が今と似てるよねってさっきおっしゃっていましたけど、似て非になるものでもあるんですね。2007年のときのあのムーブメントは、僕はものすごく刺激を受けました。ですからあそこで、あの宣言を徹底的に実践する会社を作ろうと思ってやってきたつもりです。
今、NISAをきっかけに動き始めたインデックス・ブームは、そういう意味ではインベストメントチェーンの意識が全体としてはまだ成熟したレベルになっていないんですね。インデックス・ブームっていうのは、記号を追っかけるというところに行き過ぎちゃっている。僕もたくさんの人と対話をする中で恐ろしいなと思うのは、実はびっくりするほど、多くの人が「S&P500に投資してます」って言います。でも、S&P500が何なのかを全く知らない。全く中身を知らないただの商品の名前だと思っている。では、なぜ知らないかというと興味がない。興味がないけど動画をネットで見て必ず儲かるって言っている。だから買わないと損だと周りの人にも言われたと言っている。ここ最近、買った人の中にそういう人は山ほどいますよ。さっき画面で必ず相場が下がる時が来ると言っていました。この時にまたぞろかなり多くの人が自然に淘汰されて転んでいってしまう。こういう予想は、我々みんな、しておかなければいけない課題だと思います。
ちょっと話がずれましたが、やっぱり一番、僕自身のモチベーションだったのは、まさにこの日本の資産運用業界をちゃんと本格的な高度なものにしなきゃいけない。そこに必要なのは、まさに本格的なプロフェッショナルのアクティブ運用であるということです。それは環境の変化ももちろんあります。過剰流動性が解消してインフレ前提の社会になれば、必然的に真っ当な銘柄選択をきちんと丁寧にリサーチして行っていくアクティブファンドは、これまでよりはるかに容易にインデックスを凌駕するリターンを上げてくるはずです。これは歴史が証明しています。
ですから、それをきちんと実践するということは日本の資産運用業をさらに自立して発展させるためにも絶対必要不可欠なことであって、これを徹底してしっかりと実践し、そこに共感の投資家をきちんと作り上げて、一緒に目標と思いを共有して動いていくことが必要でしょう。これがおそらくインベストメントチェーンをこの日本の中で理想とするには絶対必要だろうということで、残った人生、これを徹底していこうと思っています。
後半の質問の答えは今のことで、この共感というのをどうやって作っていくかは答えがないんですけど、澤上さんとか岡本さんがずっとやり続けてきた、それから、僕もその後ろを追っかけてやってきました。一人一人努力し、どぶ板で対応して、そして一人一人の理解を深めて共感をいただいて、それを長期投資マネーという形で凝縮させて、同じ方向を向いて、ちゃんと長い時間、次の世代に向けてお金を動かしていく。これは意思を持った長期投資マネーです。そしてこの意思が体現されることこそが、例えば日本株ファンドであれば、日本の産業界をちゃんとお金が良くしていく、お金が強くしていく。産業界が強くなっていくことによって、ちゃんと投資した我々にもリターンが返ってくる。そのリターンをもう一回使っていく。この循環こそがインベストメントチェーンですから、こういう相互理解をちゃんと世の中に定着させていく。これは資産運用業界の大事な使命だと思います。これを頑張りたいと思います。
岩城 みずほ ありがとうございました。
(分析 FIWA)