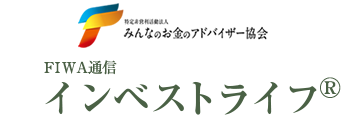【Vol.263】シンガポール駐在を終えて – 若⼲の税制⾯での考察を交えて
FIWA監事 北村勝信(公認会計⼠・税理⼠)
FIWA監事の北村勝信と申します。私は、普段は会計事務所に⾦融税務の専⾨家として勤務しており、2022年〜2024年9⽉までシンガポールに赴任していました。本稿では、駐在を通じて感じたシンガポール⽣活の魅⼒を振り返るとともに、⽇本と異なる特⾊を持つシンガポールの税制について、⽇本の投資家の⽬線も交えて若⼲の考察をできればと思います。なお、本稿記載の内容は筆者の私⾒であり、所属組織の⾒解とは関係ないものである点申し添えます。
シンガポール⽣活の魅⼒
シンガポールは、東京23区とほぼ同じ広さという⼩さな都市国家ですが、その中に、⽇系企業が1,000社以上進出しており、滞在する⽇本⼈の数も3万⼈超、街中には⽇系飲⾷店、量販店などが多くあります。JETROのデータによれば、⽇本の対外・対内直接投資でもシンガポールはアジア地域で1位(フロー、2023年)となっており、街中でも⽇本の存在感の⼤きさを常⽇頃感じていました。
シンガポールには、狭い⾯積の中に同窓会や県⼈会、同好会といった様々な⽇本⼈コミュニティがあります。決して仕事⽬的だけではありませんが、そういった場に参加することで新たな交流が⽣まれ、ビジネスにつながることもありました。また、クライアントの何⼈かとは、同じコンドミニアムに住んでいたり、⼦どもが⼩学校の同級⽣であったりしました。⽇本にいるよりも、クライアントとの距離感が近く、オン・オフ双⽅の場で交流を深められる点は、シンガポールの⼀つの醍醐味であったように思います。
年間を通じて気温が27℃程度で、⽇中は暑い(というより⽇差しが熱い)ですが、朝・⼣は海⾵もあり気持ちのいい気候です。治安も⾮常によく、⼦どもを安⼼して連れまわすことができるなど、私個⼈としては⽇本よりも安全と感じました。多くの⽅が気にされるのは物価ですが、特に⾼いのはコンドミニアムの賃料、外⾷費であり、その他は⽇常⽣活でそこまで物価を意識することはあまりありません。各種インフラも整っており、総じて、住みやすい、快適な都市であると思います。
シンガポールは他⺠族国家であり、休⽇に街中を歩いていると中国・インド・マレーや欧⽶の⽂化が融和した多様な⽂化に触れることができます。そういった多様さを垣間⾒ることは、私だけでなく、家族にとってもよい刺激となったようです。全く余談ですが、シンガポールは、インドやバリに近いからか本場のインストラクターによるヨガが盛んで、男性のヨガ⼈⼝も多いため、私も連れられてヨガにチャレンジしました。
また、魅⼒の⼀つとして、空港が近く、海外へのアクセスが良いことがあります。現地の同僚も旅⾏好きな⼈が多く(円安の影響もあり⽇本旅⾏ブームのようです)、まとまった休みが取れるときには、近隣諸国を家族や友⼈と旅⾏することが⼤きな楽しみでした。
シンガポール税制についての考察
税制は、各国で異なります。⽇本との⽐較でみた場合のシンガポール税制の特徴的な点は以下のとおりです。
- 法⼈税・所得税は低税率で、相続・贈与税はない
- キャピタルゲイン・配当は⾮課税
⽇本とシンガポールの税制の主な相違点
| ⽇本 | シンガポール | |
| 税率 | 所得税(住民税・復興特別所得税を含む)︓ 最大56%. 法人税(地方税を含む実効税率)︓ 約30% 相続・贈与税: 最大55%. 消費税: 10%. | 個人所得税: 最大24% 法人所得税: 17%. 相続・贈与税︓ なし GST: 9% |
| 個人所得税の特徴 | ||
| 譲渡所得 | 課税 | 基本的に非課税(資本所得に該当する場合。その他の場合は。個人所得税率で課税) |
| 配当 | 課税 | 非課税 |
| 国外所得 | 課税(居住者の場合) | 基本的に非課税 |
シンガポールは国策として低税率による外資誘致を掲げています。特に、個人に対する税に目を向けると、シンガポール居住者は投資所得に対する課税が優遇されており、相続・贈与税も存在しないことから、起業家、富裕層、高度プロフェッショナル人材などの呼び込みに繋がっていると考えられます。
こういったシンガポール税制上のメリットをみて、「資産をシンガポールに移してはどうか」、「シンガポールに移住してはどうか」といった考えを持つ方もいらっしゃるかと思いますが、その場合、日本の税制との関係に気を付けてプランニングする必要があります。
代表的なものとして、法人税・所得税の観点からは、日本には、「外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)」という課税制度があります。これは、タックスヘイブンなどの軽課税国を利用した租税回避を防止するための制度です。本制度には複雑な適用要件がありますが、本制度が適用されてしまうと、日本の居住者である株主がシンガポールに法人(ペーパーカンパニーなど)を設立した場合、そのシンガポール法人で生じる所得は、(配当の有無にかかわらず)日本の居住者である株主の所得に合算され、日本の税率で課税されることになります。
また、相続税については、仮にシンガポールに移住したとしても、日本人の場合、相続発生前10年以内に日本国内に住所があった場合は、引き続き国外財産・国内財産の両方が日本の相続税の課税対象となってしまう点に留意が必要です。
上記の場合、いずれも、シンガポール税制上のメリットは享受できない可能性があります。本稿では紙面の関係上、詳細な解説はできませんが、これらの論点を含む国際所得税・国際資産税は、両国の税制を踏まえた総合的な検討が必要なことから、税務の中でも複雑な領域であり、予期せぬ課税を避けるためにも、専門家を交えた事前の慎重な検討が必要と考えています。
終わりに
筆者は、2年という短いシンガポール生活を経験して、シンガポールは、生活面・税制面の双方から魅力的な国であり、今後も発展していくだろうと感じるに至りました。日本とシンガポール間のヒト・モノ・カネの往来が以前にも増して活発になるあたり、個人としても、今回の駐在経験で得た知見を活かした貢献ができればと思う次第です。
(文責FIWA®)