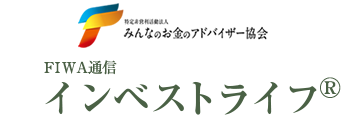【Vol.259】FIWAマンスリー・セミナ講演より(講演1)
人生お金でつまずかないためのお金の話
市民グループ「良質な金融商品を育てる会」(フォスター・フォーラム)世話人
(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)代表理事副会長
永沢 裕美子氏
レポーター:赤堀 薫里
永沢 裕美子氏 プロフィール
1984年に東京大学教育学部を卒業し日興証券(株)に入社、企業調査や資産運用業務等に従事した後、Citibank.N.A.(Tokyo)に転職し個人投資部の立ち上げ等を担当。
退職後、2004年に有志とともに「良質な金融商品を育てる会」を立ち上げ、金融分野での消費者活動を行なっている。
金融審議会委員(2009年〜2018年、現在は専門委員)を務め、「顧客本位の業務運営に関する原則」や「国民が身につけるべき金融リテラシー4分野15項目」の策定に関わった他、国民生活センター紛争解決委員特別委員(2010年〜2019年)、金融広報中央委員会・金融経済教育推進会議委員(2013年〜)、金融庁・参事(2016年〜、金融行政モニター委員)等。この間、お茶の水女子大学大学院(生活経済学)、早稲田大学法科大学院を修了し、現在お茶の水女子大学大学院にて「金融教育論」等を担当する他、 (株)山口フィナンシャルグループ、(株)ヤクルト本社等の社外取締役を務めている。
2011年から日本最大の消費者団体であるNACSに参加し、2018年から現職。消費者庁・消費者教育推進会議委員、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ)副理事長等を務めている。
今、金融経済教育といえば、資産形成のための金融経済教育というのが世の中の主流だと思いますが、それだけでいいのかなと思っています。私は消費者団体の代表をしているので、疑問に感じることもあります。お金の知識やリテラシーは、基本的にはやってみて身につけるもの。座学よりもまずはやって、「しまった」と思うような経験をして、そして学んでいくものだと思っています。座学は大切ですが、勉強ばかりしていても身につかないもの。やってみて初めて考えるということだと思います。人生七転び八起き、しかし、中にはお金に関しては立ち直りが困難なつまずきがあることも事実であり、そういうケースが近年増えてきています。
今の相談現場で若い人が一番引っ掛かっているのが副業トラブルです。将来が不安、老後2,000万円問題を引き金として皆さん非常に自分の老後に強い関心を持つようになっています。きちんと冷静に分析をすればそれほど心配する必要はないということはわかるとは思いますが、私たちの世代と違って収入についての不安があるのでしょう。また、政府も副業を解禁する方向にあることから、副業に対する関心も一般の人たちの間に広まっていることもあります。
副業を自分で検索して副業ビジネスに触れてしまうことで、そこからトラブルになっていることも多いようです。ここのキーポイントとしては、相談員の間の専門用語である情報商材という言葉です。情報商材とは、副業や投資、ギャンブル、何でもですが、とにかく収入を得るためのノウハウ等を通して販売されている情報のことです。
契約するまでは内容を確認できない。買ってみると価値がないものであることに気づきます。しかし、これは詐欺と言い切れないものになるため、契約をしてしまった以上はなかなか難しい。それでも、消費生活相談に相談をすれば、契約の過程をつぶさに相談してクーリングオフが使えたり、契約の取り消しが主張できたり、全額もしくは一部のお金が返ってくることもあります。泣き寝入りをしないでほしいということです。
それから何でもインターネット上で契約するときにはスクリーンショットを撮るという習慣を身につけるようにしてほしいです。これは相談員ならではのポイントです。とにかく記録はスクリーンショットを撮るということが、後の対応のためには必要でありポイントになります。また、今、本当に投資詐欺が増えていますが、きっかけは訪問などではなく、SNSになってきています。SNSで若い人も上手い話と思って出資したら実は実態がない投資詐欺だったということが増えています。やはり、本物の投資と偽物の投資話、これを見分ける目を育むことが必要です。
投資詐欺の手口は、非常に古典的なものが繰り返し使われています。例えば、自転車操業。配当が支払われているから安心と思っている方が多いようですが、これはポンジー・スキームと言われます。ポンジーさんというアメリカの人が右から左へお金を流す手法を開発したということで古典的なものですが、繰り返し使われています。突然に配当の支払いが止まっておかしいと思った時には、もう連絡がつかなくなり、すでに倒産させています。逃げられて回収が困難になるということになります。
世の中に上手い話はないことを肝に銘じましょう。ただそれだけではなく、登録業者かどうかということを必ず確認してください。確かに金融機関悪者論みたいなことが語られたりします。しかし、お金の取引は登録業者である金融機関以外はできません。相談をする先は金融機関ではないところでいいと思います。しかし、取引は必ず金融機関でということを徹底して教えてもらいたいと思っています。
また、海外の話が出てきて、海外の業者がというときには即、怪しいと思ってください。それから詐欺被害に遭ってしまったと気づいた時には、これは救済困難ということになります。まだ配当が払われているような状況であれば、いち早く自分で弁護士を雇い、その事業者のところで差し押さえを行い、自分のものを取り返すということが急がれるわけですが、気づいた時にはすでに遅いということになります。
唯一救いとしては振り込み詐欺救済法があります。犯罪が立件されて、万が一お金が残っていたときにはその残金から取り返すことができるということです。これは救済法を利用することができますが、お金を直接、手渡したり、郵送してしまった場合は、対象になりません。いずれにしても、消費生活センターや警察に相談してください。救済は難しいけれど、あなたの通報で次の被害を防ぐことができるということになります。何か救済できると思っても、なかなか難しいというところは理解いただく必要があると思います。
講演では、冒頭プロフィールのご紹介と、なぜ、NASC(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)から、「20代、30代のあなたに読んでほしいお金の話~人生、お金でつまずかないために~」という冊子を制作されたのか、その背景と伝えたかったことを解説くださいました。また新機構の設立にあたり、今後の懸念点と期待についてお話くださいました。
(文責FIWA®)
Free Discussion
参加者|金融経済教育推進機構がスタートし、認定アドバイザーは500~600人とか、それぐらいでスタートすると言われています。でも、それは誰なのか。金融機関に所属していない、キックバックを受けていないとか、その理念は素晴らしいですが、実際のところ誰がなるのだろうか。この辺なにか見えてらっしゃることがありますか?というのが1点。
それから金利の大事さという話で、住宅ローンの話です。日本で変動金利の人が7割以上だと思いますが、今、現在の負担を考えるとある意味、当然と言えば当然な気もします。でもその低金利が常態化したがゆえの何かの麻痺みたいなことがあるような気もする。これは金融機関も含めて金利のことをよく分からない時代が続いていたのではないかなと思うところがあります。この2点についてお願いします。
永沢|まず前半部分です。私は直接に関わっているわけではなく、金融経済教育推進委員会のメンバーとしてずっと参加しているその聞いた範囲でのお話になります。やはり金融機関勤務者を排除してスタートするということで決まっているので、だいたい独立系の方で、FP協会の方が中心となり、何回もお話は重ねているようです。その中で登録される方、認定を受けたいという方はエントリーされているようです。そうすると地方にはそのような人が本当にいないようで、
今までの金融広報アドバイザーをされている方にお願いせざるを得ないだろうということです。実は金融広報アドバイザーの中には十分に本当に金融教育をやれるのか?という方がいらっしゃることも事実です。実は、地方の金融広報アドバイザーは各都道府県にすべて任せています。金融広報中央委員会というのはただの事務局としてまとめているだけであって、教材作りはしますが、今までの金融広報アドバイザーの人選はすべて都道府県に委ねられ、教育委員会が担っているところもあれば、消費者行政を担っているところもありとさまざまです。
やはり元金融機関に勤めていた方、それから学校の校長先生が多いです。金融機関に勤めていた方は、金融には詳しいけど、偏るかもねという不安はあります。ここは教育して何とかなると思います。しかし学校の校長先生はいいお話をしてくれると思いますが、どうなんでしょうね。金融庁もちょっと悩んでいました。当初のところはお願いしつつも、次の推薦のときにはそれなりにしっかり勉強していただいて合格すれば続くけれど、ダメだったら降りてもらおうかというお話だと聞いています。今までの金融広報アドバイザーを中心としながら地方を補っていくということになるでしょう。
今回、この新機構が立ち上がり、都道府県の方と何とか連携を取ろうとしていますが、ここが大きな鍵になるでしょう。各都道府県それぞれ独自に金融広報委員会を展開してきています。そこに人も連なっているので、この新機構の思う通りに本当に動くのかどうか、認定アドバイザーを含め、人に関しては難しいところかなと思います。
また、私は個人的には金融機関にいる方は全く排除するのではなく、試験を受けて宣言をしてもらい、かつお話しされたことを録音してAIにでもかけて、発言の中に問題がある方についてはダメというように落としてしまえばいいだけで、外でそういう活動を本当にしたいと思う方であれば、会社の仕事は会社、外の金融教育は金融教育と分けてくれるのではないのか?一律に金融機関に勤めている人がダメという発想はどうなのかなと思います。また、販売金融機関の方ではなく運用会社の方に、もう少しこういうものに関わっていただくようなインセンティブが働くようなことをしたら、人材も少し充実できるのではないかと思っています。
住宅ローンの話、後半のもう一つの面については、その通りだと思います。日本の場合、この金利政策が政府の思惑で結構コントロールされてきたため、私たちが本当に金利というのは経済の体温だということをすっかり忘れてしまった。体温は冷え切っていたこともありますが、冷え切っていたものプラスこのように長く続いてしまったことは、政府が介入しすぎることにあるのではないかと思います。その意味でこの教育にも、国にはあまり介入してほしくない。機構が立ち上がったとしても、岡本さんもされているし、私も引き続き、民での草の根の活動はすごく大事だと思っています。
参加者|私は今、教育委員会の教育委員という学校教育に関わる仕事をしています。金融教育をしている人という認識を持ってもらうことが大事だと思い、4年目ですがやってきました。私は授業で投資の話や資産形成の話をするところまで全然いっていないので全くすることもなく、金利の話とか今日お話しくださったことを手前味噌ですけど、ちょっとできているかもと思いながらお話を伺っていました。
ただ、教育委員会の人から私を一言で表すとしたら、投資のことを教えている人と表現されてしまいます。私は投資のことなんて一言も授業で言っていないのに、そのように言われてしまうイメージがあるようです。それを打開する方法は何か。どのようにすれば間違った認識で私のことを見られないのか。兵庫県伊丹市というところに住んでいますが、そこだけでも全然進まないのでどうしたらいいのかというのを日々課題に感じています。どのようにアプローチをすればそれが打開できるのか、ヒント、アドバイスなどがあれば教えてください。
永沢|私は経済のお話をするときに、経済はやはり、私たちの資本主義の社会は株式会社が中心に成り立っている。公務員でなければあなたのお父さんもお母さんも株式会社にお勤めかもしれませんね?というところから始まり、その基本の話をしているだけなので、経済教育という言葉が賢すぎて難しそうに見えるなら、ネーミングを変える必要があるかもしれませんね。経済を語るというと、すごい評論家みたいになって、遠いものに思われるので、その辺が皆さんの認識として欠けているのかなとは思います。まずは一回聞いてもらう。話している内容が本当に世の中の話をしているに過ぎないのであって、世の中で必要な知識の話、物の考え方を話しているということを、学校の先生方はお勤めされているのでご存じないのでしょう。
岡本|株式会社の仕組みとか、金利の仕組み、そういう一番基本的なところは当然、学校で教えるべきことでしょう。今、教えていないのであれば教えるように変えればいいし、この時代だからどんどんいろいろなところを変えて反対する人は押し切ってやってしまうよりしょうがないですね。その方が教えられる方はずっと喜ぶわけだし、有り難いわけだからね。別に悪いことを教えているわけじゃないですから。
永沢|その意味ではJ-FLECというか新機構に期待することがあるとすれば、教科書のあり方や教え方について、もう一度、再検討をお願いするということは、私たちが意見書を出して内容についての見直しをしていった方がいいと思います。家庭科はすぐ投資信託を教えようということになっているようです。
岡本|それは大きな問題です。ただね、これは基本的に草の根運動から始まるべきもので、一人一人の個人の生活者がいかにきちんと物事を理解して自分にとって必要な行動を取るようになっていけるか。それをサポートする人たちはいるわけです。それは教育機関じゃなくて一人一人の人間に寄り添って、実際の生活の中で運用に対する伴走者として働いていく。それが私は本来のアドバイザーというものだと思います。
アドバイザーというと、いろいろな人がいろいろな言葉をいろいろなところで使いやすいから使っているけれど、人生を通じて資産の運用を共に歩んでいく伴走者だからこそ先に出て走ってはいけない。でも間違ったことをしそうになった時にはちゃんと正してあげなければいけない。そういう立場の人がどんどん増えてくることによって、生活者の中にアドバイザーという一つの仕事があって、それを使ったら意外に良かったよ、という人が増えてくれること。
それからもう一つは、アドバイザーそのものの質を高くすること。これは単に教科書に出ているようなことをしっかり覚えるとか、そういうことを機構で教えるのかもしれない。でも大事なことは、その人の人生のことを本当に考えてあげる、ということです。それはすごく必要なことじゃないかなと思います。アメリカでは、実際にアドバイザーというのは原則そういう人たちです。そのように日本もなっていくのであろうとは思っています。
ただ、今いろいろ試行錯誤の時代です。大事なことは長期的な視野を持つということ。10年後にやっぱりあの時はあのような方向に向かってよかったなということと、一部の人たちじゃなくて、業界や、国民全体のレベルが上がっていくということ。その二つしかないです。生活者全体が、5年や6年ではなくて、10年、20年、30年経った時に、ああ、世の中はやっぱり良くなっているなと、そのようにみんな思ってくれるような活動を我々もしていきますし、機構にもそういう意識でやってもらいたいなと思う。そうすると、それなりに価値のあるものにはなるだろうと思います。今日は大変いいお話を伺えてよかったと思います。どうもありがとうございました。
(文責FIWA®)