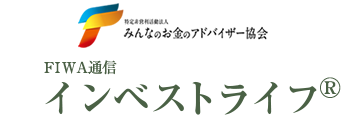【Vol.270】FIWA®会員ミーティング報告
岩城理事長が語る「FIWA®のこれまでの足跡」
今日はご参加いただきまして、本当に感謝しております。このFIWA®サムライズ勉強会ですけれども、元々は私が2011年にスタートしたセミナーです。今回84回目です。当時は、そして今もかもしれませんが、セミナーとか勉強会というと、後ろに商品がついてくる、つまり主催者が売りたい商品があり、セールスが目的というのがすごく多かったんですよ。
それで、良質なセミナー、誰でも参加できるセミナーを作りたいと思ったのがきっかけです。
中野晴啓さんや渋澤健さん、藤野英人さんなどにもご登壇いただいたりして、本当に草の根的にやっていました。その後、2019年にNPO法人みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA®(以下、FIWA®)がスタートしましたのでFIWA®にこの活動を移しました。そして今回は初めての大阪での開催です。
FIWA®は2019年に設立をいたしました。私自身は2009年に独立系FPとして開業をしたのですが、相談業務をしていますと、セカンドオピニオンを求められることが非常に多かったんですね。FPの方にご相談に行ったら、いいアドバイスを受けたのだけど、最後の最後に「これいかがですか」って金融商品を勧められる。家に帰ってググってみると、その商品は自分のニーズが合ってない。評判もよろしくないということで、「これってどうなんでしょう」と、ご相談に来られるわけです。
それで、これは、「誰が金融商品を売ることを目的としていないアドバイザーか」を見える化をする必要があると強く思ったのがきっかけです。
2018年につみたてNISAが始まったのですが、その1年くらい前から、金融庁の今井さん、現在はFIWA®のアドバイザリーボードのメンバーにもご就任いただいていますが、「つみたてNISAの父」と呼ばれている。その今井さんと相談して「NPOを作りたいよね」っていうことをずっと話していたんです。
そこで、たくさんの有識者の方に「金融商品を売らないことをはっきりわかるようにするためのNPOを作りたいんだけど、協力してもらえませんか」とご相談に行ったんです。でも、みなさん、「考えていることはいいことだけど、日本でまだアドバイザーだけで食べていくのは難しいんじゃない?」、「時期尚早なんじゃない?」と言われました。
どうしようかなと思っていて、最後に岡本さんに相談に行ったんですね。実は岡本さんが長年開催してきていたマンスリーセミナーに私は2010年ぐらいから通っていました。私が頼んだら岡本さん断りづらいだろうな、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちがありましたので、遠慮していたんですね。しかし、最後の最後に、今井さんと一緒に岡本さんにご相談に行ったら、岡本さんが全面的に同意してくれて、「ぜひやろう」ということで、あっという間にパパパッと決まったんですね。(岡本加筆:実は私も長いアメリカでの体験から「これからは日本でも本物の専業アドバイザーが絶対必要!」と思っていました。そこに今井さんと岩城さんが飛び込んできたのです)
そして、2019年にFIWA®が設立されました。今日お話するのは、この設立にあたって岡本さんと私が長い時間をかけて議論を重ねてきたことです。全くその頃から想いはブレてないっていうことを会員の皆さんにもぜひ知っていただきたいと思っています。
まず、なぜアドバイザーが必要なのかということを徹底的に議論しました。生活者が自らお金に向き合う時代にこれからなるということ、つまり、「将来の自分を支えるのは今の自分自身」なんだ。「そういう時代だよね」って言うことなんですが、やっぱり生活者の方のお金の知識が不足しているのに誰に相談に行ったらいいのかという、相談先が不明瞭であるということが問題でした。多くのアドバイザーと名乗る方が実は、金融商品を販売したり、金融機関との関係があったりということで、お客様本位での仕事をしていないことが多い。利益相反が生じているという事実が問題だということになりました。
それでは、どういうアドバイザーを作ろうかということで決まったのが「FIWA®」という頭文字で表される行動指針です。この頭文字の最初は「F」。フィデュシャリー」、お客様に忠実な助言、そして「I」インディペインデント。金融商品販売を営む組織から独立した立場であること、そして「W」はウェルス(富)、お金のことだけではなくて、人生そのものの豊かさを考える。お金の面では資産全体で考えるという視点、そして最後の「A」はアドバイザーですね。これは知識もある。そしてプロとしての確固たるプライドと倫理感を持つプロフェッショナルであるということを要件としています。
このFIWA®のアドバイザーとしてふさわしい条件はどんなものか随分、議論しました。まず、金融商品を一切販売しないこと、直接的、間接的に金融機関との関係がないこと、販売に関わるコミッションを受け取っていないこと、そしてアドバイス料のみが収入であるということ、そしてフィデュシャリー・デューティ宣言を金融庁に届けることを認定の要件としました。これはもともとは2014年ぐらいから、当時の森元金融庁長官が「フィデュシャリー・デューティが非常に大事だ」ということを言い始めていたわけです。その後、金融庁が金融機関にフィデュシャリー・デューティ宣言を半ば義務的に金融機関に提出をさせたという経緯があったのです。個人として仕事をしている私は金融庁に「出せ」とは言われてもいなかったのですが、私は個人としてフィデュシャリー・デューティ宣言を勝手に作って送ったんですね。私のホームページにも掲載ました。
岡本さんが「アドバイザーこそフィデュシャリー・デューティ宣言が絶対に必要」ということで、FIWA®の認定資格でも「個人として」のフィデュシャリー・デューティ宣言を提出するということを認定の条件としました。さらに資格として、経験、倫理観を備えているということ、本当のプロフェッショナルとして「お客様のために」という、「顧客ファースト」ということを一番に掲げるということを考えました。
そしてミッションとしてでは、アドバイザーの育成・認定・支援に加えて、生活者の皆様にしっかりと金融知識を身につけていただくというミッションを掲げました。その時の資産形成の基本として、今もずっと岡本さんが言ってらっしゃる、毎月、全世界に分散された低コストのインデックスファンドを積み立て投資する。それを相場に関わりなく続けること、一発勝負の投資はしない、感情に流されない冷静に理解できる投資をする、こういうことを資産形成の基本にしましょうということにいたしました。(岡本加筆:ともかく、最低限、これだけはすぐに始めるべきということで「できるだけ若いうちから毎月、収入の一定比率を全世界の株式インデックス投信に積立投資をする、相場変動にかかわらず、それをリタイアするまで絶対に止めない」という「75文字の資産形成」と作ったのです)
そしてFIWA®の活動としては、アドバイザーの、育成、認定、支援をする。その一環として岡本さんがずっと続けていらっしゃったFIWA®マンスリーセミナー(現在はFIWA®サロイン塾)と私が続けてきたサムライズ勉強会をFIWA®の活動の柱ということにしたわけです。目指す目標としては、販売に依存しない本物の、純粋なアドバイザーを育成すること、信頼できる相談環境を整備すること、そして顧客ファースト、お客様ファーストが当たり前の文化を作るこの3つを目指すこととしました。しかし、FIWA®を設立してから「FPがFPをジャッジするのか」とか、「金融商品を売ることが、そんなにいけないことなのか」とかいろいろ言われました。
厳しいことをたくさん言われて、私もかなり落ち込んだりしたんですけれども、当時から私たちが一貫して言い続けているのは、アドバイザーとセールスというのは全く違う職業である。両方とも生活する上で必要だし、両方とも顧客本位でなければならない。自分たちのためにではなくて、お客様ファーストということは両方ともに大事である。しかし、「異なる職業である」ということです。
急に世界が変わるということはずっとなかったのですが、転機が訪れたのが2022年です。岸田内閣が「資産所得倍増プラン」を結成したわけです。岸田元首相は、「NISA拡充の実現のためには、顧客本位のアドバイザーを増やすこと、金融教育の強化をするということをセットにして行うべきだ」と考えているということをはっきりおっしゃいました。
金融審議会の顧客本位タスクフォースと合わせて、社会保障審議会の企業年金個人年金部会をスタートしました。私もずっと金融庁と何度も何度も議論を重ねていたのですが、でも、実は、心の中では半信半疑だったんです。フィデュシャリー・デューティ宣言させたけれども実態はちっとも変わっていない。KPIを作らせたりしていましたが、結局、役所をやることってこのぐらいなのかなってということをすごく思っていたのですね。
でも「それじゃダメですよね」ってことを散々議論して、どうやら本気でやるつもりなのだということを感じるようになりました。そして何より、顧客本位ということが再び俎上に乗るとうことに価値があるのだと思うようになってきた。私は、今度こそは絶対にこのチャンスを逃さずに世の中を変えたいと思い、強い決意を持ってこの両審議会に出席をしました。かなり嫌がられましたが、別に私が審議会議員を外されようが、どうされようがそんなことは関係ないという気持ちで言うべきことを言い続けました。
そして2024年、ついにNISAが拡充され、そしてJ―FLECが設立されました。J―FLECが「認定アドバイザー」を認定することで、日本でもようやく、セールスとアドバイザーが明確に分離されたということになります。J―FLECの安藤理事長は、個別の商品の推奨販売はあくまで金融機関でするものであり、認定アドバイザーは、そうした判断をするために生活者のリテラシーを高めていく」とおっしゃっています。
つまり、アドバイザーには教育的な役割も期待されているということです。まさにFIWA®がずっとやってきたことです。これを国が「自分たちもやるんだ」ということで、方針として相まってやっていく、という流れになりました。ようやく世の中が少しFIWA®に追いついてきたということでしょうか。
でも大切なことは、FIWA®はさらに純度を高め、より一段高みを目指さなければいけないということです。FIWA®の会員のみなさま、そしてFIWA®の会員になろうかなと思っているみなさま、みんなで手を取り合いながら日本の生活者が物心共に豊かで幸福な人生を送れるようにするという壮大な社会貢献をしていきましょう。
(この記事は5月24日に大阪で開催されたサムライズ勉強会における岩城理事長の講話の前半部分を岡本が加筆修正したものです)